

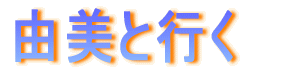
| 9、 父が、ホテルの風呂から上がってくつろいでいると電話が鳴った。 「お父さん、金印はもう見た?」 「ここに置いてあるよ」 「今から見に行ってもいいかなあ」 「いいよ」 「じゃあ行くね」 由美は、すぐにやってきた。 「あっ、これ昨日撮った写真ね」 父が、パソコンにデジカメで撮った写真を写し出していた。 「志賀島は本当に綺麗だったわね。夕日の写真はどうだった?」 「芸術作品みたいなのもあるよ。ほら、これなんかもいいだろう」 「わあ、綺麗」 「次の写真が、一番良く撮れているよ」 「本当だ。どこか、コンテストにでも出品したらどうかしら。夕日が海に反射して幻想的よね」 「その場にたまたま通り合わせて、こんな綺麗な夕日が見られたなんて、本当にラッキーだったよ」 由美は、その画面を見ながら、あの感動したひと時を思い返していた。 「ねえ、金印を見てもいい?」 「ああ、いいよ」 父は、袋の中から紙に包まれた小さな箱を二つ取り出した。 「ええと、こちらだ」 「そっちは?」 「これは、ネクタイピンだよ」 「お父さん、ネクタイなんか滅多にしないのに」 「まあ、記念にと思ってね」 父は、紙に包まれた小さな箱を由美に手渡した。 「わあ、ドキドキする」 由美は、包装紙を丁寧に開けた。 「桐の箱に入っているのね」 「何と言っても国宝だからね」 「これは、レプリカだけど」 由美は、木箱の蓋をそっと開けた。 「わあ、金印だ」 「おお、レプリカとは思えないよ」 「触るのが恐れ多いって感じだわ。お父さん、ちょっと出してみてよ」 「そうか。では」 父は、紫の紐と共にそっと持ち上げた。 「見た目より重いなあ。何か歴史の重みを感じるよ」 「印字の面は?」 父が裏返しにした。 「本物と変わらないわね」 「きっと同じ判が押せるよ」 「お父さん、漢委奴国王になっちゃうよ」 「なるほど。って、誰も思わないよ」 「当たり前じゃない。ねえ、ちょっと持ってもいいかしら」 「ああ、いいよ」 父が箱に戻したので、由美は紫の紐を持って金印を手にした。 「本当ね、小さい割に重さがあるわ」 「でもこれが、どうして志賀島で発見されたんだろう」 父は、金印と一緒に買ったパンフレットを開いた。 「一七八四年に発見されているそうだ」 「じゃあ、二百二十年程前のことね」 「その年の二月二十三日に、甚兵衛というお百姓が、田の水はけを良くしようと作業をしていたそうだよ。すると大きな石がいくつか出てきて、それを取り除こうとしたら、石の間から光る物が出てきたそうだ。それが金印だったということなんだ」 「そして、それが発見された場所が、あの金印公園の所ということなのかしら」 「そうだね」 「でも、田畑があったと思われるような場所は見当たら無かったわ」 「昔は、狭いながらもあったらしいよ。そしてその甚兵衛は、兄の元奉公先だった商人米屋才蔵のところに届けたそうだ。その才蔵が、知り合いだった学者亀井南冥に鑑定を依頼したところ、南冥は、それが光武帝から拝受した金印だと見抜いたということだ」 「その南冥という人はすごいわね。良くそんなことを知っていたわね」 「当時開館したばかりの藩校の館長だったそうだけど、本当に良く分かったものだよ」 「それで、どうなったの?」 「そこで、南冥と才蔵は奉行に買い取り許可を求めたそうだ。ところが、藩は、それを許可せず、金印の研究をただちに開始したんだ。そのことは、すぐに全国的に知れ渡り、ここから金印論争が始まったらしい」 「良かったわね、その時に金印のことが分かる人がいて。もし、藩が許可していたらどうなっていたか分からないところよね」 「本当だよ。溶かされて表具にでもなっていたかもしれないよ。とまあ、ここまでは特に何も問題が無いように思えるだろう」 「そうねえ。特に疑問はないわ」 「ところが、謎がいっぱいだそうだよ」 「謎って?」 「当時の志賀島の過去帳に甚兵衛という百姓はいないそうだ。それだけでなく、古文書には、志賀島農民秀治・喜平、叶崎より掘り出すという記述が残っているらしい」 「それはどういうことなの?」 由美は、金印を箱に戻した。 「甚兵衛は、はたして志賀島の百姓だったのか。でも、『百姓甚兵衛口上書』が、三月十六日にお役所に提出されているんだよ。届け出たのは甚兵衛、掘り出したのは秀治・喜平ということなのかなあ」 「そう言われると、経緯がちょっと変ね。甚兵衛にしても、その人たちにしても、届けるならまず、お役所に届けないかしら。商人の手へ先に渡って、それを鑑定した学者が奉行に話したから、お役所に知れたわけでしょう」 「だよねえ。まずは、お金にしようとしているよなあ」 「いくら、自分の土地から出てきたとしてもなんか変よね」 「さらに変なのは、発見された場所だよ。南冥が、発見場所まで地図に記した鑑定書を残しているんだよ。でも、その場所をいくら調べても、それらしい遺構は何一つ見つかっていないらしい」 「ちょっと、見せて」 由美も、印刷されたその南冥による鑑定書を見た。 「確かに、はっきりと場所を叶崎だと特定しているわね」 「でも、どうしてあの場所なんだろう」 「大きな石の下にあったということは、落としたとかじゃなく、埋めたということだものね。まあ、分からないようにこっそりと隠したとしか考えられないわね」 「まあ、そういうことなのかなあ。歴史のミステリーだよ」 「でも、このパンフレットもよく調べてあるわね」 「ああ、かなり詳しいだろう」 由美は、面白そうなので続けて読んだ。 「ふうん。十年ほど前に、福岡市が全島調査をして、その時に、周辺の海底や地層の探査までしたんだって。島の4ヶ所で何本も試掘をしたそうよ」 「それは、すごい力の入れようだね」 「残念ながら、結局は何も分からなかったんだって」 「それは、本当にご苦労様な話だよな」 「でもね、そのお陰で成果もあったそうよ。昨日夕日を見たときに小さな島があったでしょう」 「ええと、沖津島だったかな」 「あの側にある中津宮で古墳がみつかったんだって。それが唯一の成果だったようよ」 「古墳だって?」 「そうよ」 「どこから」 「だから、ほら」 「ちょっと、見せて」 父は、その記事をくいいるように見た。 「たしか、島の写真があったよなあ」 「最初の方にあったわ」 父は、ページをめくった。 「そうか。あそこには古墳があったのか。ほら、ここを見てごらん。この部分が丸く盛りあがっているだろう」 「あっ、本当だわ。古墳ね」 「そこまでは、分からなかったよなあ。ちょっと待てよ・・・?」 父は、何か考えている様子だった。 「もしかしたら・・・」 「どうしたの?」 「もしそうだとしたら辻褄が合う。そして、謎も解けるよ」 父は、何かが分かったようだった。 「だから、何が?」 「金印が、本当は何処でどういう経緯で発見されたのか、見当がついたんだよ」 「本当に?」 「そりゃ、あくまで想像だよ。でも、それですべての辻褄が合うよ」 「ねえ、どういうことなの」 「教えて欲しい?」 「勿体ぶらないで教えてよ」 父は、由美の耳元でこっそりと話した。 「大きな声じゃ言えないけど」 「何?」 「これは、盗掘だよ」 「ええっ、盗掘?」 「おそらくあの志賀島の北端にある中津宮古墳から掘り出したんだよ。盗掘の跡の写真も載っているだろう」 「まさか、金印が実は盗掘された物だなんて信じられないわ」 「どうも、あのあたりを見た時から何かありそうで気にはなっていたんだけど、まさか古墳があったとは思わなかったよ。きっとその古墳に金印が埋められていたんだよ」 由美は、あまりのことに驚いてしまった。 「あの場所にねえ」 「そりゃ、叶崎をいくら探しても無駄だよ。最初から何も無かったんだから」 「でも、鑑定書には場所が叶崎だと特定されているのよ」 「あたりまえだよ。盗掘したら出てきましたなんて書くわけにはいかないだろう。お縄になるどころか、首が飛びかねないよ」 「本当に、盗掘だったのかなあ」 「だから、最初からお金にしようと商人の手に渡ったんだよ。きっと金印だけでなく他にも副葬品があったんだろう。おそらく、その中には金印が何を意味するのか分かるような物もあったのかもしれないよ」 「じゃあ、南冥も盗掘だと知っていたということ?」 「おそらくね。きっと、それが分かるような物は処分されたんだろう。しかし、金印だけは、あまりの歴史的遺産だったので、お役所の手に渡ってしまったという訳だよ」 「なるほどね」 「だから、後で、辻褄を合わせるために口上書が書かれたんだよ。北の端で見つけたから、誤魔化すために反対の一番南にしたんだろう」 「じゃあ、金印が発掘されたのが、その中津宮古墳だとしたら、その被葬者は金印の持主ということ?」 「そう、きっと漢委奴国王と言われたその人だよ」 「ええっ、本当に?」 「おそらく間違いないだろう。この志賀島を含む地域は奴国と言われていたし、その北の端は、何処に向いてる?」 「大陸の方かな」 「つまり、漢の国に向いた一番見晴らしのいい場所に埋葬されているんだよ。だとしたら、その人をおいて他にはいないだろう」 「そして、その王の遺品として金印も一緒に埋葬されたということなのね」 「そう。ただ、金印は、王の死後も後継者があるいは受け継いでいたのかもしれない。だから、後の後継者が埋葬したということも考えられなくもない」 「後でね」 「それは、何とも分からないけれど。その墓は、おそらく金印を授かった漢委奴国王に間違いないだろう」 「となると、金印が何処に埋められていたのかも、発見された経過がよく分からなかった理由もはっきりするわね」 「そう。ただ、あくまで、お父さんの勝手な推理だけどね」 「でもこのパンフレットにも、甚兵衛の口述書から、埋められていたのはこの古墳ともとれると書いてあるわ」 「ひょっとしたら、同じように盗掘と考えられているのかもしれない。微妙な表現だよなあ。きっと、盗掘だとは言えないのかもしれないよ」 「それにしても、この金印が造られたのは二千年ほど前なのよねえ」 「そうだね。漢の国から二千キロも離れた奴国まで届けられたことだけでも大変なことだよ」 「それが、今の時代にまで残り、こんな感動を与えてくれるなんて本当にすごいわね」 「その重大さが分かった南冥や保存に動いた藩の役人の努力などがあってのことだよ」 「そうね。本当によく残ったものよね」 「時代を超えた歴史物語だよ」 「なんか、ミステリー小説を一冊読み終えたような気分だわ」 「それは良かった。じゃあ、明日はいよいよ本命の高山だよ」 「そうね。どんな風景が見られるのかな」 由美は、少し高揚した面持ちで自分の部屋に戻った。 |
![]()


![]()
![]()
邪馬台国発見
Copyright (C) 2008 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.