|
3、
そして次の日の朝、由美が目を覚ますと父も間もなく起きた。
「あっ、もうこんな時間か。さあ早く用意をして出かけよう。今日は、今年一番の行楽日和だから混むかもしれないよ」
「そんなに慌てなくても大丈夫よ」
朝食を済ませ、二人は奈良へ向かった。
奈良公園の近くに来ると、東大寺周辺は観光客でいっぱいだった。
奈良国立博物館には、すでに人の列ができていた。
「正倉院展は人気があるのね」
「お父さんも一度見たかったんだよ」
二人は入場券を購入して館内に入った。
五十六回目となる正倉院展であるが、今回も歴史的遺産が数多く展示されていた。
「お父さん、やっぱり間近で見ると感激するね」
「よくもこんなに状態良く残されていたものだよ」
しばらく展示物を見ていたが、急に父の足が止まった。
「お父さん、どうしたの」
「ほら、これを見てごらん。鑑真だよ」
「鑑真?」
「そう、何度も何度も渡航に失敗しながらも、やっと東大寺にたどり着いたあの鑑真の書だ」
「歴史で習った人の書いた物が、この目で見られるなんて驚きだよね」
「こんな立派な筆さばきは、滅多に見られないよ。偉大なる鑑真の書といった風格が感じられる」
「でも、鑑真は視力を失ってしまったと習ったよ。字は書けたのかしら」
「これが、誰かによる代筆とはとても思えないなあ」
「じゃあ、字が書ける程度の視力はあったのかもね。あるいは、誇張された話だったのかな」
「最後が『三月十八日鑑真状白』と読めるだろう。鑑真が三月十八日に書状で述べたということだと思うんだけど。他人の名前をこんなに慣れた字では書けないよ」
「確かに達筆だよね」
「字には書いた人の人格が現われると言うから、本当に立派な人だったんだろうね。いつまでも見ていたいよ」
「でも、そういうわけにはいかないわ」
父は、ようやく歩き出した。
「そう言えば聖武天皇の遺品とか見かけないよなあ」
「見なかったね」
「正倉院は、聖武天皇の遺品を保管するところから始まっているんだから、何か出展してないのかな。できれば、聖武天皇の書が見てみたいから、由美も探してくれよ」
「いいわよ」
父は、足早に展示物を見て回った。
「どこにも無いなあ」
「無いわね。でも、どうして聖武天皇の書なの?」
「東大寺の始まりも、正倉院も、大仏もみな聖武天皇が関わっているだろう。どんな人だったのだろうかと思ってね」
「全部見たけど正倉院展には無いわ。でも常設の展示場にはあるかもしれないわよ」
「じゃあ、そちらに行ってみようか」
常設展示場にも、仏像など数々の文化財が並べてあった。
父は、聖武天皇の宸筆について案内係の女性に尋ねた。
「どこかに、聖武天皇の書いた物はないでしょうか」
「こちらは、聖武天皇の字だと言われていますが、他に展示物はありません」
二人が、その女性の指し示す方を振り返ると、そこには『東大寺』と大きな石に彫られた物が展示してあった。
「東大寺の入口に掲げられていた物です」
よく寺院の門に名称が表示してあるが、どうもそれのようだった。
「毛筆と違うから、良く分からないわね」
「そうだなあ。しかし、これを見ても聖武天皇が東大寺の建立の中心にいたことが解かるよ」
「とりあえず他の展示物も見ようよ」
「そうしようか」
残りの展示物を見て、地下通路を抜けると出口に出た。
「もう一度聞いてみるか」
「また聞くの」
父は、展示場の入口付近に立っている学芸員らしき男性に尋ねた。
「聖武天皇の宸筆ですか。それでしたら、こちらへどうぞ」
父は、その男性について行き、由美もそのあとに続いた。
すると、その男性はなぜか玄関から外に出て、上を指し示した。
「この『奈良国立博物館』の字は、聖武天皇が書いた『雑集』の中にある文字から起こした物です」
「ほう。これが聖武天皇の字ですか」
先ほどの鑑真の字も立派だったが、この聖武天皇の字も達筆だった。
「じゃあ、こちらへどうぞ」
その男性は、多くの資料が並べられているコーナーに案内してくれた。
「以前の正倉院展にも出展したことがありますが、ここに載っている『雑集』が聖武天皇の宸筆として唯一残されているものです」
その男性は、正倉院の宝物が載っている分厚い本を開いて父に示した。
「聖武天皇の文字は、繊細でとても綺麗ですね」
父は、しばらくその本に見入った。
「そうだ、ちょっとお聞きしていいでしょうか」
「どうぞ」
「天皇は他にもいたのに、どうして聖武天皇だけ、あんなにも宝物を持っていたのでしょうか」
「それは、天皇家の血筋ですから、代々受け継いでこられたのでしょう」
「なるほどね。もうひとつだけ、すみません。どうしてこの地に奈良という地名が付いたのか、その由来についてはご存知ないでしょうか」
「それは、私には分かりません」
「そうですか。どうもお忙しいところをありがとうございました」
父はその男性にお礼を言い、その男性もその場から立ち去った。
「しかし立派な字だよ」
父は、よっぽど気に入ったのか、しばらくそこから離れなかった。
「ねえお父さん、そろそろ行こうよ」
「そうするか」
父は、まだ名残惜しそうだったが、その本を棚に戻し奈良国立博物館を後にした。
|


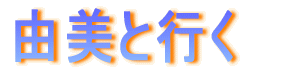
![]()


![]()
![]()