|
15、
大晦日までは、例年通り買い物や大掃除にと慌しかった。
そして明けて新年になり、家族一同で初詣に出かけることになった。
今年は、スサノオ尊が奉られているという熊野大社に行くことにした。
元旦は荒れていたが、二日になると穏やかに晴れていた。
「さあ行くよ」
軽く朝食を済ませて出発した。
山陰自動車道を走り、松江の手前を左折して南へ行くと、意宇川沿いにめざす熊野大社があった。
露店もたくさん出ていて、行き交う人々の中には、着物姿の若い女性も見受けられた。
鳥居をくぐり本殿の前に来ると、参拝者で一杯だった。
妻や娘達は早速おみくじを買っていた。
父は、手にしていたカメラで本殿や周囲の建物を撮影した。
そして、熊野大社を紹介している本やパンフレットを購入し、早速、建物の側でその本をめくった。
すると、昔から伝わる神事について書かれているのが目に付いた。
『鑽火(さんか)祭?』
毎年十月十五日に、出雲大社の宮司が「古伝新嘗祭」に使用する神聖な火をおこすための燧臼(ひきりうす)と燧杵(ひきりぎね)を受け取りに、熊野大社にやってくるという神事だ。
その時に、出雲大社が持ってくる長くて大きな餅に対し熊野大社の亀太夫は、その餅の出来栄えが悪いと口やかましく言い立てる。
そのあと、亀太夫は餅を受け取り、燧臼と燧杵が渡され、出雲大社の宮司により百番の舞が舞われて神事が終わる。
古伝新嘗祭では、この燧臼と燧杵できりだされた神聖な火(鑽火)で食事が用意されるという。
『変わった神事だよなあ。いつ頃からこの鑽火祭をしているんだろう』
父は、その後をめくると鑽火祭の由来が書かれていた。
出雲国造家の祖先と言われる天穂日命(アメノホヒノミコト)は、熊野大神櫛御気野命(クマノオオカミクシミケヌノミコト)から、燧臼と燧杵を受けたと言われている。
それ以来、出雲国造家は、その燧臼と燧杵できり出された火を使うことになったとしている。
『火がとっても神聖なものだったんだ』
出雲国造は、その火を斉火殿で絶やさないようにして、一生その火で調理した物しか食べなかった。
そして、家族といえどもそれを口にしてはならなかったという。
『熊野大神櫛御気野命とは、スサノオ尊を意味しているから、それだけスサノオ尊や火が尊崇されていたということなんだろう』
父は、その次に書かれていた文字に釘付けになった。
[神聖な『火』の発祥地でもある熊野大社は、別名『日本火之出初之社(ひのもとひのでぞめのやしろ)』といわれている]
『日本? 熊野大社に日本の名称がついている』
父は、何度もそれを読み返した。
『いつから呼ばれていたのだろう。もしやこれが、日本国の名称の起源なのかもしれない』
父は、胸がドキドキしてきた。
そして、由美を探して声をかけた。
「ちょっと由美、大変な物を見つけてしまったよ」
「お父さん、ほら大吉だって」
横にいる明代が、先ほどのおみくじをうれしそうに見せていた。
「おっ、それは良かったじゃないか。じゃあ、後でお父さんも引いてみようかな」
「お父さんどうしたの」
由美が、父の側に来た。
「ほら、これを見てごらん」
「どこ?」
「ここだよ」
父は、先ほど読んだ『日本』の名称の書いてある所を由美に見せた。
「ひのもとひのでぞめのやしろ。そうだ、日本のことを以前はひのもとと呼んでいたと聞いたことがあるわ」
「今にまで伝わる鑽火祭の神事で、出雲大社は、熊野大社から神聖なる火を授かっているんだ。火の元だから、日の本となったのだろうか」
由美も、鑽火祭の神事について書いてある所を読んだ。
「出雲国一の宮として、熊野大社の方が格が上だよと言っているような神事ね」
「亀太夫は、熊野大社の神職の中でも位が低い方だそうだ。その亀太夫ですらその神事においては出雲大社の宮司より優位に立つんだよ」
「熊野大社の威厳を誇示しようとしているみたいね」
「それは、熊野大社にはスサノオ尊が奉られているからだと思うよ。背後には、スサノオ尊がいるから、出雲大社の宮司と言えども亀太夫に従うんだよ。そのスサノオ尊と日本という国名が結びついたんじゃないかと思えるんだよ」
「どういうこと?」
「倭国という名称は中国から付けられたようなものだっただろう。そこで、国を統一するにあたり、自分達で新しい名称を考えた時にだよ。この国で最も偉大な王であるスサノオ尊にあやかろうとしたんじゃないかな」
「なるほどね。一番由緒正しきスサノオ尊から国名を授かろうとしたわけね」
「当時の人々にとっては、最も威厳があって恐れ多い名称だったんじゃないかな」
「なんか、今の時代の儀式でもそんな光景を見かけるわね」
「そう考えると、日本と何故付いたのか納得いくだろう」
「そうね」
そこに明代がやってきた。
「お父さん、もうお店の方へ行こうよ」
いつまでも本殿のあたりにいるのも飽きてきたようだ。
「そうか。じゃあ行こうか」
父は、おみくじと小さいお守りを買って参道を下った。
露店の周辺は、昼時とあって参拝帰りの客で賑わっていた。
お好み焼きやたこ焼き、イカ焼き、りんご飴など、いろいろな店が並んでいた。
「どうしよう、ここで昼食にしようか」
「そうだなあ、そうするか」
いろいろな種類を買い、近くの椅子に腰掛けてみんなで分け合った。
「お好み焼きが結構おいしいね」
「こんなにおいしいりんご飴は初めて」
初詣にはあまり出かけたことが無いので、みな行楽気分で楽しそうだった。
「たまには、こんなのもいいね」
妻も、横でたこ焼きを口にしている。
しかし父は、先ほどの事がまだ気になっていた。
その時、ある事を思い出した。
「そうだ、由美。分かったよ」
「どうしたの?」
「そう言えば、旧唐書にあったのを思い出したよ」
「お父さん、食べている時くらい、古代史は忘れようよ」
明代が、少しあきれていた。
「こんな話をしながら食べると、なお一層おいしく食べられるというものだよ」
「それは、お父さんだけだよ」
「そうかなあ」
「それより、さっきお父さんの買ったおみくじはどうだったの?」
「おみくじかい。ちょっと待ってよ」
父は、鞄に差し込んでいたおみくじを取り出して広げた。
「おお、お父さんも大吉だよ。商売もうまくいくと書いてあるよ」
「そうなるといいんだけどね。そんなのあてにならないわよ」
妻が横で言った。
「まあ、お遊びだよ。その時だけでも楽しくなるじゃないか」
「恋愛運は?」
明代が笑いながら聞いていた。
「恋愛運なんか聞いてどうするんだよ」
「まあ、いいから教えてよ」
「そうかい。ええとねえ、一線を超えるなだって」
「そんなこと今更言われても手遅れよ。ねえ、お母さん」
「もう何を下らない事言ってるのよ。さあ、そろそろ帰りましょうか」
妻の言葉で昼食休憩が終わり、みな立ち上がり駐車場へ向かった。
しばらく走っていると、疲れて眠ったのか後ろの席が静かになった。
「お父さん、さっき言いかけていた旧唐書のことって何だったの?」
横に座っていた由美が聞いた。
「前に、旧唐書に遣唐使のことが書かれていると話しただろう」
「日本国の誕生を伝えたけれど、唐に不信に思われてしまったということだったわね」
「そう、そこにね、日本は旧(もと)小国と書かれているんだよ。旧だから古くから日本という国があったということなんだよ。でも、日本なんて国がそれまであったなんてどう考えても理解できなかったんだよ」
「そんなこと聞いたこと無いわよね」
「そうだよ。それで、ふとそのことを思い出してね。スサノオ尊の奉られている熊野大社を中心とした意宇地方に王朝があり、そこが日本と呼ばれていたとしたら辻褄が合うと思わないかい」
「熊野大社のあたりが?」
「そう。そこから南に行くと日野町や日南町があるだろう。日の本で日本、日の南で日南、日の野で日野。日本があった名残ではないだろうか」
「でも、そういう記録は何も残っていないわよね」
「日本書紀で、他の王朝の存在はすべて否定されたから、日本という国があったことは徹底的に消し去られたのではないだろうか」
「それが、熊野大社にだけは密かに語りつがれていたということかしら」
「熊野大社の本を見ても、出雲大社は大きく発展したけれど熊野大社は、一時、かなり衰退したと書かれていたよ。出雲大社は、優遇されていたが、熊野大社は冷遇された。つまり、スサノオ尊隠しが背景にあったんじゃないだろうか」
「じゃあ、鑽火祭の神事はある意味それを伝えているのかしら」
「そう考えると、熊野大社がその歴史や存在を必死に訴えているように思えないかい」
「でも、スサノオ尊にあやかって国名を付けておきながら何だか変よね」
「だから、日本書紀に日本は紀元前六六〇年に建国したなんて書いたから、辻褄が合わなくなったんだよ」
「日本国の誕生って、本当の所はどうだったんだろうね」
「都合の悪い事は、数十年前のことでも無かったことにしてしまおうとするくらいだから、古代史においてはなおさらだろう」
「日本の歴史ってそんなことでいいのかなあ。他の国の人から見たら誠実さの無い国民に思われてしまうわね」
「いや、一部の勢力はそうかもしれないけど、いつかこの国の歴史が根本的に見直される日が必ず来るよ」
「そうだといいよね」
由美は、そんな時が本当に来て欲しいと思った。
山陰自動車道を東に向けて走っていると、大山が見えてきた。
頂上には雲がかかっていたが、富士山を思わせるような綺麗なすそ野が広がっていた。
「明代、ほら見てごらん。大山がすごく綺麗だよ」
「あ、本当だ」
「由美、写真に撮っておいたら」
妻も後ろで目を覚まして言った。
「お父さん、ちょっとデジカメ借りるね」
由美は、右手に見える大山にカメラを向けていた。
「そうだ、玲子にも送ってあげようかな」
由美は、携帯電話を取り出し、対向車や障害物を気にしながら撮影した。
山陰の霊峰大山は、雪で白く化粧された荘厳な姿を見せていた。
今年一年が良い年になることを願いながら、西山家一行は、初詣を終えて家へ帰っていった。
|


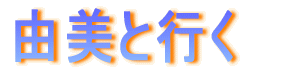
![]()


![]()
![]()