|
12、
九州から帰る日の朝も快晴だった。
「今から出ても図書館が開くまでには、少し早いかな」
おだやかな朝日を浴びながら、二人は福岡へ向けて出発した。
九州自動車道を北へ向かって走っていると筑紫野市に入った。
父には、かねてより疑問に思っていることがあった。
筑紫という地名を小学校の社会の時に見かけ、何故そう付いたのか不思議だった。
今回も博物館でその事を聞いてみたが、分からないということだった。
九州は『くす』と読めなくも無い。
それで、九州の地という意味で、地九州(ちくす)から由来していないか。
あるいは、九州を治めるという意味で、治九州(ちくす)から由来していないか。
これらを、尋ねたが、九州は時代がもう少し新しいのであり得ないとのことだった。
では、筑紫という地名の由来はどこにあるのだろうか。
運転中の父の目に、『筑紫野市』の表示板が映った。
その瞬間だった。
「そうか。分かったよ!」
「お父さん、急にどうしたのよ」
「こんな簡単なことが、今までどうして分からなかったのだろう」
「だから何が?」
「筑紫の由来だよ」
「筑紫?」
「そうだよ。子供の頃から疑問に思っていたのが、今やっと分かったんだよ」
「どういうこと?」
「筑紫の地名は、紫にあったんだよ」
「はあ?」
「だから、紫を作っていたんだよ」
「紫を?」
「そう、古代、大宰府周辺は紫の産地だったんだよ。この列島で一番の生産量を誇っていて、大陸の方にも輸出していたほどの重要な産業だったんだよ」
「そんなにたくさん?」
「万葉集にも、紫は『韓人の衣染むといふ紫の…』と詠われているのを見たよ。あの時にどうして気が付かなかったんだろう」
「万葉集には、そんなことまで詠われているのね」
「紫を作る産地だから筑紫なんだよ。そうだったんだ。どうして、こんな簡単なことが分からなかったのだろう」
「それって、お父さんの思い過ごしじゃないの」
「そうかなあ」
「でも、それが仮に正解だったとしても、別にどうということでもないわよ」
由美には、ただ地名の由来が思い当たっただけのことではないかと思えた。
「とんでもない。万葉集に『あかねさす 紫草(むらさき)野行き 標野行き …』という歌があるだろう」
「額田王の歌でしょう。大海人皇子が『紫草の にほえる妹を 憎くあらば …』と答えているわね」
「それが詠われたのは、紫草の産地である大宰府周辺だということが、かなり濃厚になってくるんだよ」
「そうか。万葉集はますます北九州を詠っているということになるのね」
「そうなんだよ」
「なるほどね」
そんな話をしている間に、車は福岡市に入った。
都市高速を経て博物館の駐車場に到着したが、やはり隣の図書館の開館にはまだ時間があった。
博物館の前には広い庭があり、しばらくそこにある椅子に腰掛けて待つことにした。
穏やかな秋の日差しが暖かかった。
「福岡はいいよなあ」
「そうね」
「昔の倭国の人たちも、こうしてのどかに過ごしていたのかなあ」
「どうだろうね」
「仏教の盛んだった倭国だから、きっと信心深い人たちが多かったんだろうなあ」
「仏教の伝来した百済とかなり深い関係だったみたいだしね」
「その百済が滅亡の危機に瀕したため、倭国は百済に兵を送った。しかし、結局それが元で倭国は滅ぼされてしまった」
「白村江の戦いね」
「でも、その派兵は侵略的だったかどうか疑問に思えるんだよ。むしろ百済の要人を、唐や新羅の攻撃から救出するのが目的だったんではないかな」
「救出?」
「だから、兵も戦闘的ではないからぼろぼろにやられてしまった。そして、この国まで逃れてきたが、結局はやられてしまった。その最後が、壬申の乱と言われているように思えるんだよ」
「壬申の乱が?」
「最後まで追い詰めて百済王の息の根を止めたのが大海人皇子、つまり天武天皇ではないかな」
「へえ、そういう見方もできるんだ」
「天武天皇は、新羅系の王だったという説もあるよ」
「じゃあ、白村江の戦いの後は、唐や新羅の影響下にあったということになるの?」
「そういう状態だったことも考えられるよ。その後、藤原一族がこの国を五世紀近くも支配するようになっただろう。あるいは、藤原氏は、唐の勢力だったのかもしれない。さあ、そろそろ時間だよ。行こうか」
「そうね」
二人は、図書館に入り二階へ上がった。
「これだよ」
父は、先日の本を手にした。
「さて、コピーしようか。でも、どこが必要になるか分からないから、結局全部コピーしてしまいそうだよ」
「それなら買った方がいいんじゃないの」
「そうだなあ。でも、手に入るかなあ」
「後ろに連絡先があるでしょう」
父が、裏表紙をめくると著者の電話番号が書いてあった。
外へ出て、携帯電話で連絡を入れると、すぐに送ってくれるとのことだった。
「助かった。コピーしなくて済んだよ」
「じゃあ、これで帰れるね」
「悪いけどもう一度戻っていいかい」
「ええっ、まだ何かあるの?」
「これ以外にも、古代大牟田のことについて書かれた本があるかもしれないから、それだけチェックして帰ろうよ」
「まだ見るの」
「重要な所だからね」
二人は、また館内に入った。
「大牟田関連だよ」
「分かったわ」
二人は古代史のコーナーをしばらく探したが、特に目を引く本は無かった。
「じゃあ、もう帰ろうか」
「お父さん、大牟田じゃないけど、ほら、こんな本があったわ」
由美が、何か気になる本があったようで、父に見せた。
「どんな本かな」
父は、その本のタイトルを見て思わず叫んでしまった。
「ええっ、本当に!」
「お父さん、声が大きいよ」
父は、すぐに中を見た。
「あの世界遺産にも指定されている法隆寺が、大宰府の観世音寺から移築されているそうだよ」
「ええっ、あの観世音寺から?」
「どうしてなんだろう」
父は、しばらく考え込んでいた。
由美も父からその本を受け取り、読んでみたが、その理由はよく分からなかった。
「そうかあ、考えられなくもないなあ」
「何故そんなことをする必要があるの?」
「どうしても、そうせざるを得ないようなことをしてしまったからだろうな」
「どうして? 作りたければ新しくいくらでも建てられるでしょう」
「ところが、新しいと意味が無いんだよ」
「ええっ、どういうこと?」
「あの日本書紀を創り上げた勢力だよ。それくらいのことは考えただろう。まあ、もうそろそろ行くか」
父は、その本のタイトルと出版社を記録して博多駅へ向かった。
駅に着くと、次の新幹線までにはまだ少し時間があった。
「ちょっと、お茶でも飲むか」
「お父さん、遅くならない?」
「この程度なら大丈夫だよ」
父は、もう少し娘と一緒にいたかった。
二人は、ステーションビルの中の喫茶店に入り飲み物を注文した。
「長かったようで、でもあっという間に過ぎてしまったわね」
「ああ、でもこんな楽しい旅行をしたのは初めてだよ」
とりあえずは、やるべきことをやり終えた満足感で一杯だった。
「いろんなことがあったわね」
「そうだね。万葉集の疑問をたどっていたら、滋賀や奈良に止まらず九州にまで来てしまった。でも、古代史の謎を解くカギが、九州にあったのには驚いたよ」
「そうね。古代史探求の旅は、まだ当分終わりそうもないわね」
「ああ、まだ何か隠された秘密が潜んでいるように思えるよ。それに最大の謎が残っているからね」
二人は、テーブルに置かれた飲み物を口にした。
「何なの、最大の謎って」
「この国がなぜ日本国と名付けられたのかということだよ。それが、この国の一番の謎と言ってもいいかもしれない」
「日本という国名ねえ。あまり考えたことが無かったわね。それにしても、名前も、成立も謎に包まれた国ってどういうことなのかしらね」
「そうだね、分かっているようでも、しかしその本当の所は謎だよ。じゃあ、そろそろ行こうか」
改札口を出て乗り場まで行くと、もうたくさんの人が並んでいた。
「お父さん、一つだけ聞いていい?」
「どんなことかな」
「さっき言いかけていた法隆寺が移築された理由って何なの?」
「新生日本国にとって、倭国や出雲など過去に王朝が存在していた形跡が残っていると都合が悪いと言っただろう」
「そうだったね」
「だから、古い建物が残っているのも具合が悪かったんだろうな」
「だったら、そんなことはして欲しくないけど、壊してしまえば済むじゃない」
「お父さんもそう思ったよ。でも、良く考えてごらん。日本国は、紀元前六百六十年から続いている国だと書いたんだよ。その国の都に新しい建物ばかりだとどうなる?」
「そうか、古い建物が必要だったんだ」
「だから、古くからあった都にするために観世音寺だけでなく、各地にある古い建物が奈良や京都に集められたのではないかな」
「なるほどね」
「すべてがそうではないだろうけど」
「そう言えば、大津市史に書かれていた、当時、建材を再利用した例が多いとあったのは、このことも意味していたのかしら」
「あるいは、大津宮もその頃に移築されたのかもしれないよ」
その時、新幹線が入ってきた。
「じゃあ、続きはまたゆっくりと」
「くれぐれも気をつけて帰ってね」
「由美もな」
「家に着いたらメール入れてね」
「ああ」
由美は、列の流れと共に車両の中に消え、出発を知らせるベルが鳴った。
動き出した車両の窓越しに由美が手を振っている。
父も手を振り、その姿を見送った。
「さあ、帰るか」
父は、由美と九州に来ることができて本当に良かったと思いながら帰路に着いた。
|


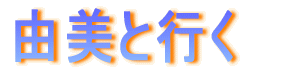
![]()


![]()
![]()