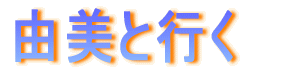|
8、
「表紙の写真は、こちらですね。では、みなさんで見出しを考えてみてください」
西山は、今夜も中学校PTA広報誌の編集会議に出ていた。
「もう少しアンケートの分析を深めて、内容を検討してみてはどうでしょうか」
「そうですねえ」
長倉先生と特集のグループが、校正を前に置きながら議論している。
西山も加わったが、どうまとめるか中々難しい状況にあった。
その日は、結局、各自が分担して、もう少し考えてくることになった。
表紙や、行事のグループもそれぞれ初校の検討を終え、長倉先生に引継ぎをしてその日の編集会議を終えた。
「どうもお疲れ様でした。長倉先生、正倉院展は良かったですね。先週の金曜日から奈良、伊勢、明石と回ってきたんですよ」
「西山さんも正倉院展に行かれましたか」
「囲碁盤が出ているとなると、これを見逃すわけにはいきませんからねえ」
編集会議の片づけをしながら、ちょっと雑談になった。
「伊勢や明石にも行くとなると、ちょっと大変でしたでしょう」
「まず、二見が浦で、朝日を背景に夫婦岩を撮影したかったんです。車中泊で待機したのですが、やはり今の時期には無理でした」
「それは、残念でしたね」
「まあ、天気が良かったので、とりあえずは、夫婦岩の写真は撮れました。しかし、そのあと行った伊勢神宮は、やはりなんか謎めいていました」
「そうですか、明石へは?」
「今、万葉集にある柿本人麻呂の歌に疑問を持っていて、一度、実際その詠われている場所に行ってみたかったんです」
「何か分かりましたか」
「その疑問は解けたように思ったのですが、新たな疑問が生まれてしまいました」
西山は、人麻呂の歌を紹介して意見を聞こうとも思ったが、あまり遅くなっては申し訳ないので、それ以上詳しくは話さなかった。
「人麻呂の歌は、非常に格調高いですが、謎の部分も多いですよねえ」
もう一人の担当の吉野先生が、片付けながら話しかけてこられた。
「本当にそうです。どう解釈したらいいのか、難しい歌が多いですね」
「人麻呂は、お隣り、島根県の石見地方でも数多くの歌を残していますよ」
「そうですよねえ。何でしたっけ、『高角山の木の間より』というような歌はよく聞きました」
「『石見のや 高角山の木の間より わが振る袖を 妹見つらむか』人麻呂は、石見の国の初代国司として四年間赴任していたと言われています。その任期を終えて、都へ帰る時の歌のようです。愛しい妻を残して帰るのが相当辛かったのでしょう。実は人麻呂は石見の生まれだとか、石見で亡くなったとか、そういった伝説も残されています。人麻呂縁の神社もいくつかありますよね」
「そうですねえ。そう言えば万葉集には石見を詠った歌がいくつかありましたね」
恒之は、旅の歌八首にこだわっていたが、もう少し他の歌も調べてみるのもいいかと思った。
『結局、人麻呂に聞かなきゃ分からないのかしら』
明石で由美の言った言葉が思い出された。
片付けも終わり、恒之は、中学校を後にした。
家に帰ると、妻の洵子と娘の明代が風呂上りに何やら話しているようだった。
「あら、お帰りなさい。お疲れ様」
「ただいま、今日は編集会議の後、吉野先生からいい話を聞いたよ。あの先生、柿本人麻呂にかなり詳しそうだったなあ」
「吉野先生は、社会の先生だからね」
中学三年になる明代が教えてくれた。
「なるほどね。やはり、歴史に関わることには詳しいんだ」
「吉野先生は、若いし、かっこいいから人気があるんだよ」
「ほう、そうか」
恒之にも、分かるような気がした。
そして恒之は、早速二階に上がり、石見にまつわる万葉集の歌を調べることにした。
すると、第二巻にいくつか並んでいた。
そこへ洵子が、上がってきた。
「まだ何か調べているの?」
「ああ、ちょうど今、人麻呂が石見を詠っている歌を見つけたよ」
「遅くまで熱心ね」
そう言いながら、横で洗濯した衣服の片付けを始めた。
恒之は、引き続き人麻呂の歌を読んだ。
《柿本朝臣人麻呂、石見国より妻を別れて上がり来る時の歌二首 併せて短歌》
石見の海 角の浦廻(うらみ)を 浦なしと 人こそ見らめ 潟なしと 人こそ見らめ よしゑやし 浦はなくとも よしゑやし 潟はなくとも いさなとり 海辺をさして にきたづの 荒磯の上に か青く生ふる 玉藻沖つ藻 朝はふる 風こそ寄せめ 夕はふる 波こそ来寄れ 波のむた か寄りかく寄る 玉藻なす 寄り寝し妹を 露霜の 置きてし来れば この道の 八十隈(やそくま)ごとに 万度(よろずたび) かえり見すれど いや遠に 里は離りぬ いや高に 山も越え来ぬ 夏草の 思ひしなへて 偲ふらむ 妹が門見む なびけこの山
「ねえ、人麻呂はどんな歌を詠っていたの?」
片付けを終えた洵子が、めずらしく興味を抱いたらしく、恒之に聞いてきた。
「吉野先生が話しておられた、人麻呂が国司の任期を終えて石見を離れる時の歌だよ」
洵子も、その歌をじっと見ていた。
「何を意味しているのか、よく分からないわ」
「その横を見てごらん。現代文に訳してあるだろう」
「これね」
洵子は、そちらをしばらく読んでいた。
石見の海の 角の海辺を 浦がないと 人は見るだろうが 潟がないと 人は見るだろうが えいままよ うらはなくても えいままよ 潟はなくても (いさなとり) 海辺をめざして にきたづの 荒磯の辺りに 青々と生い茂る 玉藻沖の藻は 朝吹きつける 風が寄せるだろう 夕方押し寄せる 波で寄って来よう その波と一緒にあちこちと寄る 玉藻のように 寄り添って寝た妻を 置いてきたので この道の 曲り目ごとに 何遍も 振り返って見るが いよいよ高く 山も越えて来た (夏草の) 思いしおれて わたしを偲んでいることであろう 妻の家の門口が見たい 平たくなれ この山よ
「人麻呂さん、かなり辛かったようね。曲るたびにもう一万回かというほど振り返ったとあるわ」
「後ろ髪を引かれるというか、引きちぎられるほどの心の痛みを感じているようだよ」
「妻の家が見たいから、山よ平たくなれだって」
「その後に反歌が二首あるよ」
洵子は、その歌を読んだ。
石見のや 高角山(たかつのやま)の 木の間より 我が振る袖を 妹みつらむか
笹の葉は み山もさやに さやけども 我は妹思う 別れ来ぬれば
「この初めの方の歌は、聞いたことあるわね」
「そうだね。同じような反歌がもう一首紹介されているよ」
石見なる 高角山の木の間ゆも 我が袖振るを 妹見けむかも
「《或る本の反歌に日(いわ)く》とあるから、まあそういうことなのね。ねえ、また同じように長い歌があるわよ」
「二首とあったから、これが二つ目の歌ということかな」
二人は、次の歌を読んだ。
つのさはふ 石見の海の 言(こと)さへく 辛(からの)崎なる いくりにそ 深海松(ふかみる)生ふる 荒磯にそ 玉藻は生ふる 玉藻なす なびき寝し児(こ)を 深海松の 深めて思へど さ寝し夜は いくだもあらず 延(は)ふつたの 別れし来れば 肝(きも)向かふ 心を痛み 思ひつつ かえり見すれど 大船の 渡(わたり)の山のもみち葉の 散りのまがひに 妹が袖 さやにも見えず 妻隠(ごも)る 屋上の山の 雲間より 渡らふ月の 惜しけども 隠らひ来れば 天伝ふ 入日さしぬれ ますらをと 思えへる我も しきたへの 衣の袖は 通りて濡れぬ
「似たような歌に思えるわよね」
「その次の、訳文を見てみようか」
(つのさはふ)石見の海の (言さへく) 辛の崎にある 暗礁に 深海松は生えている 荒磯に 玉藻は茂っている 玉藻のように 横たわって寝た妻を (深海松の) 深く思うが 一緒に寝た晩は 幾らもなく (延ふつたの) 別れて来たので (肝向かふ) 心せつなく 思いつつ 振り返って見るが (大船の) 渡の山の もみじ葉が 散り乱れて 妻の袖も はっきりとは見えず (妻隠る) 屋上の山の 雲間を 渡り行く月のように 名残惜しくてならないが その姿が見えなくなった時分に (天伝ふ) 夕日も落ちて来たので ますらおだと 思っているわたしも (しきたへの) 衣の袖は 涙で濡れ通ってしまった
「たくましい男だと思っていたのに、着物の袖が濡れ通ってしまうほど、涙を流したってことよねえ。人麻呂さん、そこまで彼女のことを思っていたのね」
「そうだね。反歌も見てみようか」
「反歌は、やはり同じように二首ね」
青駒が 足掻(あが)きを速み 雲居にそ 妹があたりを 過ぎて来にける
秋山に 落つるもみち葉 しましくは な散りまがひそ 妹があたり見む
「人麻呂さん、本当に辛かったのね。馬がどんどん走っていくので、名残惜しそうよ」
「いよいよ出立の日だよ。人麻呂は、朝起きると身支度をして、関係者や近隣の人たちにお別れの挨拶をしてまわるんだ。そして最後、彼女も含めた親しい人たちに見送られながら馬で出発したんだ。でもね、名残惜しくて、離れたくなくて、四年間過ごした石見の地を、我慢できずに、何度も何度も振り返って見るんだよ」
「あら、何かまるで人麻呂になったみたいね」
恒之は、どことなく自分の体験に似ているように思えてきた。
「すると、石見の地で出会った人たちの顔が次々と浮かんで来るんだよ。あの人、この人とね。そして、峠を越えていく頃、夕暮れ時を迎えた。いよいよ、もうこれで石見の地ともお別れだと思った瞬間、耐え切れなくて人麻呂は、人目をはばかることなく嗚咽してしまった。『馬を、馬を止めよ』そう言って馬から下りて、眼下に見える石見の地を、しっかりと目に焼き付けておこうとしたんだろう。拭いても拭いても、流れ出てくる涙を、袖でぬぐいながらね」
恒之は、自分の卒業の頃や、人麻呂のその時の気持ちを考えたら、もう涙が一杯にあふれてきた。
「あらら、人麻呂のことを考えていたらあなたまで悲しくなってきたみたいね。そこまで、人麻呂の気持ちが分かるなんて、最近、人麻呂の歌に熱中しているからかしら」
「どうしてなんだろう。自分の言葉に酔ってしまったのかなあ」
恒之の思いは、なかなか人には伝えにくかった。
「あのう、感動に浸っているところ、水を差すようで悪いんだけどね」
「何?」
「こんな質問していいかしら」
「いいよ。僕だってどうせ疑問だらけなんだから」
「最初に人麻呂の歌二首とあったけど、確かにニュアンスは違うけど、なんか同じような歌が二首よね。別に、一首にまとめてしまってもいいのにと思ったの。その上、ある本の歌として、同じような歌というか、最初の歌とほとんど一緒の歌がさらに入っているのよね。どうしてなのかしら。こんな疑問を持つ方が変なのかしら」
「いや、そんな事ないよ。僕も何だか違和感があったよ」
「良かった。同じように変に思っていたのね」
「ある本に日くという注釈がついて、似たような歌が載せられることはよくあるよ。この後に出ているのもそうだよ。でも、二首と言っているからには、違う事を歌っているはずなんだ」
「違う事を歌っているって?」
「そう。じゃないとわざわざ二首なんて書かないよ」
「でも、表現は違っても、詠っている内容は、ほとんど一緒よ」
「そうだよなあ」
恒之は、もう一度二首を見比べてみた。
だが、そんなに違いはなかった。
そこで、もう一首紹介されている歌を読んでみた。
「ええっ!」
恒之は、驚きの声をあげた。
「どうしたの。何か分かったの?」
恒之は、もう一度、最初の二首を読み返した。
「そうか、そうだったんだ。そりゃ、袖が濡れるほど大泣きするのも無理はないよ」
「ねえ、何が分かったのよ」
「一首目のここを見てごらん。『玉藻なす より寝し妹を』とあるだろう」
「そうね」
「つまり、玉藻のように、寄り添うように二人して寝た妻と別れてきたと悲しんでいるんだ」
「そうよね」
洵子は、何度も読んでそれは、分かっていた。
「では、二首目のここを見てごらん」
恒之が指し示すところを見た。
「『なびき寝し児を』とあるだろう」
「そうね、これも妻だと書いてあったわ」
「そう、解釈はそうなっている。僕もそう思ってしまったよ。だから、この二首の違いや、それぞれが持っている歌の意味を見落としてしまったんだ」
「ええっ、そんなに違いがあるの?」
「大違いだよ。別々の人に捧げている歌なんだよ」
「別々の人?」
「別々の人と言うのも変だけど、『なびき寝し児』なんだよ。妹じゃない」
「妻じゃないってこと? そうなると、じゃあ、児って、子どもだってこと?」
「そうなんだよ。彼女との間には子どもがいたんだ」
「ええっ、本当にそうなの」
「原文があるだろう。それも見てごらん。兒とあるだろう。この文字に妻という意味はないよ。子どもだよ」
「じゃあ、どうして、妻と解釈されているのかしら」
「さあ、それは分からないけど、もう一首紹介されていただろう。それを見てごらん」
洵子は、恒之の指し示すところをみた。
「ほら、わざわざ『我が妻の児が』とある。妻の児とは、どう考えても、妻を意味しなくて子どもを意味することになるよ。そんなに無理やり子どもを隠す必要もないだろう。だから、最初の歌は、妻に捧げる歌で、二首目は、その子どもに捧げている歌なんだよ」
「なるほどね。それなら、二首となっている意味も分かるわね」
「『玉藻なす より寝し妹を』とあるように、数年間、妻とは、寄り添うようにしながら夜を過ごしてきたんだよ。でも、二首目は『さ寝し夜は いくだもあらず』とあるだろう。ここでは、何年も一緒にいて共に夜を過ごしたのは、幾日も無くと言っているんだ。変だろう。それは、子どもの事だからなんだよ。小さいときは、お母さんと一緒だから、そうそう人麻呂と寝ることは無かったのだろう」
「そうね。そう考えると、みな辻褄が合ってくるよね」
「だろう。だから、まだせいぜい一歳かそこらなんだよ。そんな可愛い盛りの子を置いたまま、別れてしまうんだよ。当時の事だから、いつまた会えるかなんて分からない。あるいは、もう二度と会えないかもしれない。それを考えてごらん。人麻呂でなくても号泣するよ」
「彼女だけじゃないんだものね」
恒之は、自分なんかより人麻呂の方が、はるかに辛い思いをしたのだろうと思った。
「ねえ、このすぐ後に人麻呂の妻の歌ってあるわよ」
「人麻呂の妻の歌?」
恒之は、洵子の言う歌を読んだ。
《柿本朝臣人麻呂が妻依羅娘子(よさみのをとめ)、人麻呂と相別るる歌一首》
な思いそと 君は言うとも 逢わむ時 いつと知りてか 我が恋ひざらむ
横の訳文も読んだ。
思うなと あなたがおっしゃっても 今度いつ逢えると 分かっていたら こんなにまで恋しく思いません
恒之は、言葉も出なかった。
「辛いお別れね」
「こんなこと言われたら、もう腰が砕けてしまうよ。自分なら、とても、二人を置いてなんか帰れないよ」
「そうよね。じゃあ、どうして連れて帰らなかったのかしら」
「それは、やっぱり、まだ子どもが小さかったからだよ。我が家が引っ越した時は、明代がまだ一歳になってない時だったよなあ。でも、自分達は車だったからね。当時は、そんな小さな子どもを連れての旅は、ちょっと無理だよ」
「そうね。車の中で、明代におっぱいをやってたものね。そんなこと、この時代ではあり得ないよね」
「つまり、洵子や明代を置いて、別れて自分だけ帰って来るようなものなんだよ。そりゃ、泣くだろう」
「本当かしら。清々したって、羽を伸ばす方じゃないの。でも、子どもが、もう少し大きくなってからでも、迎えに行けばいいのにねえ。そんなことは、しなかったのかしら。ねえ、万葉集のどこかに載ってないの。こんなに辛い思いをしたんだから、なんか後日談があるでしょう、普通は」
「おいおい、そんな、テレビのドラマじゃないんだから」
だが、妻の言葉で、恒之はふと思い当たる事があった。
「んんっ、後日談?」
「どうかしたの」
恒之は、ようやく人麻呂の歌の疑問が解けたように思えた。
「そうか、後日談だったんだよ。洵子、ありがとう。万葉集、最大のドラマが隠されていたんだ。これで、ずっと、ずうっと謎だったことが完全に解決したよ。ありがとう」
恒之は、思わず洵子を抱きしめた。
「ちょっと、ちょっと、急にどうしたっていうのよ。何を一人で感激しているのよ」
「いやあ、もうすっごく感謝するよ。やっぱり、由美が言ったように人麻呂に聞けということだったんだ。そうだ、由美にメールを送ろう」
「ちょっと、私に感謝するんじゃないの。どうして由美にメールなのよ」
「きっと、驚くぞう」
恒之は、もう踊りたくなるような心境だった。
【お~い、由美、例の八首の謎が、今やっと解けたよ。大感激だ。正月に帰って来たらゆっくり教えてあげるよ。由美の『人麻呂に聞いてみよう』がいいヒントになったよ。何だって? もったいぶらずに早く教えてだって。だめ~、これで帰る楽しみが出来ただろう】
恒之は、長い間、頭の中で渦巻いていた謎が解けてすっきりした。
「よしっ、これで一件落着。では、お休み」
恒之は、こんな晴々とした気分で寝るのは、本当に久しぶりだった。
「ねえ、私に感謝は?」
「またね。絶対に忘れないから」
「何よもう」
恒之とは反対に、洵子は、もうひとつ何の事だかよく分からず、狐につままれたような気分で床についた。
巷では、ジングルベルの音楽が鳴り響く時期を迎え、夜の冷え込みは、冬の訪れを知らせているようだった。
|