|
7、
「わあ、本当に布団が載せてあるのね。車の中で寝れた?」
由美が、ちょっと驚いていた。
「ああ、結構快適だったよ。あまりお勧めはしないけどね」
「勧められてもちょっとねえ」
二人は、名神高速を西に向かった。
そして国道二号線を走り、明石海峡大橋が近づくと、かなり渋滞してきた。
「このあたりは、片道一車線だからいつも渋滞してそうだよ」
「お昼でこうだから、夕方だともっと込むんでしょうね。ところで、どこに車を止めるの?」
「出てくる時にお母さんに聞いたら、橋の近くにお店がたくさん入ったポルトバザールという大きな施設があるから、きっとそこがいいだろうと言っていたよ」
「でも、お母さん、良く知っているわね」
「今度は何処へ行こうかなあって、時々旅行雑誌を買って読んでいるから、そこにも行ってみたいと思っていたのかもしれないよ」
「なるほどね。じゃあ、お母さんも一緒に来れたら良かったのにね」
「多分、無理だろう。お父さんは、観光しているように見えて、実は撮影と取材にしか興味がないから、きっと付いて来れないよ。それに、車中泊は絶えられないだろう」
「そうね、緊急時とかやむを得ない理由があるなら仕方ないけど、旅行の時は、旅館やホテルでゆっくりしたいわね」
そんな話をしているうちに、ポルトバザールの入口に来た。
日曜日だということもあり、大きな駐車場に、かなりの車が止まっていた。
そこには、お店やレストランがたくさんあったが、お昼時とあってどこも一杯だった。
「途中お昼を食べて来ていて良かったね。これから食事をしようとしたら大変よね」
「そうだね。まあ、せっかく来たんだから、ちょっと見て回るか」
「そうね」
最初は、二人で見ていたが、恒之にとってあまり目を引く物はなかった。
由美は、やはり女の子で「これ、かわいい」と言いながら、小物などを見ていた。
「ここを出た所にベンチが見えるだろう」
「ああ、あれね」
「そこで待っているよ。時間はあるから、ゆっくり見て回るといい」
「分かった」
そう言って、恒之は、外に出てベンチに腰掛けた。
妻と買い物に出かけると、妻は、買うのか買わないのかよく分からないが、あれやこれやと見て回る。
買いたい物をさっさと探せばすぐに終わると思うのだが、そうも言えず、恒之は、どこかに腰掛けて終わるのを待つ。
それでも『もう少し時間をかけて見たかったわ。あなたが待っていると思うとゆっくり出来なくて』などと言っている。
感覚の相違なんだろうか。
恒之が腰掛けているそのベンチからは、瀬戸内海がわずかに見えていた。
『そうだ、待っている間にちょっと海を眺めてみよう』
恒之は、横に置いていたデジカメを手にして立ち上がった。
建物の横を抜けると堤防があり、その先端まで行ってみた。
海面を見ると、潮の流れが結構早かった。
「ええっ、かなりの急流だなあ」
干満の時間などによっても違うだろうが、その流れの速さに恒之は驚いた。
そこからは、瀬戸内の海がぐるりと見渡せた。
『ほう、なんていい眺めだろう』
対岸には淡路島が、そして、右手には瀬戸大橋の雄大な姿も間近に見える。
心地の良い風が吹いていた。
東の彼方に目をやると、かなり大きな山並みが見えた。
『そうか、あれが紀伊半島だ。でも島って感じには見えないよ。あれを見て、人麻呂は島と詠んだのだろうか』
恒之には、ちょっと腑に落ちなかった。
『ここまで来て、「おおっ、島だ、島が見えたよ」と感動を持って詠んでいるんだよ』
紀伊半島を見て、人麻呂がそういう表現をしたとは、恒之にはとても思えなかった。
向かいには、淡路島があるが、それも考えられなかった。
『とにかく、人麻呂は西を向いていたはずだよ』
恒之は、そう思って堤防の先から西を見た。
『人麻呂が見た時は、日暮れ時で、夕日が綺麗だったのだろう』
そう思って遠くを眺めていた恒之の目に、かすかに見えるものがあった。
「えええ~、こ、これは」
恒之は、手にしていたデジカメを構えて次々とシャッターを押した。
「そうだ、由美にも知らせなければ」
直ぐに海岸沿いにある堤防の先まで来るようにメールを送った。
少しして、恒之の携帯電話が鳴った。
「お父さん、どうしたの。すぐに来いって」
「すごいものが見えたよ。とにかく、そこからまっすぐ海に向かうと堤防があるから、すぐにおいで」
「分かったわ」
由美が、少し息を切らしながらやってきた。
「どうしたの。何が見えたの」
「いいかい。通説で言えば、人麻呂は東を向いてこんな風景を見たことになるんだよ」
由美は、父が言う通りに東を向いた。
「何か遠くに山並みが見えるわね。なるほど、あれが紀伊半島なのね」
「どうだい。『島が見えたよ』って思えるかい」
「どうかなあ」
「それ以前に、紀伊半島は島ではないことを人麻呂は知っていたはずだよ。大陸からの視点なら、この列島を島と表現するかもしれない。だが、ここに暮している人たちにとって、この列島や紀伊半島を島とは表現しないだろう」
「だよねえ」
「そこでだよ。お父さんが言っていたように、人麻呂があの歌を詠った時、西を向いていたとしたら、ちょうど今ここに立って見える風景と同じような風景を見たはずなんだ」
父が、西を向いたので、由美も同じように西を向いた。
「明石海峡から西を見る景色って綺麗よね。大橋も本当に良く見えるわ」
「そうじゃなくて、もっと先の方を見てごらん」
「もっと先?」
由美は、父が言うように遠くを眺めた。
すると、由美の目に、かすかな島影が写った。
「島? お父さん、島が見える! 遠くに小さい島があるよ」
「だろう。何か感動するだろう」
「うん、やっと見えたって思えるわ」
「お父さんも、さっき見えた時は、もう感激したよ。島が見えたよ~って。きっと人麻呂はこの島を見て、あの歌を詠んだのだろうってね。ようやくここまで来たよという思いだったのかもしれない。おそらく、天候の良くない時は見えないと思うよ、だから、見えた時は余計に感動を呼ぶんだろうね」
「すごいわね。人麻呂と同じ感動を味わったのね」
「同じかどうかは、分からないよ」
「そうか、ということは、人麻呂はあの島を見て歌を詠んだのね」
「おそらく、そうだと思うよ」
「でもお父さん」
「何?」
「ではどうして、あの七番目の歌だけが、逆向きに解釈されているのかしら」
「だろう。いかにも変だろう」
「どうしてかしらね」
「とりあえず、写真は撮ったから、また考えてみるよ」
「わたしも大学の図書館に行ってみようかな。何か分かるかもしれないから」
二人は、感激の余韻を残しながら明石駅へ向かった。
「となると、何が恋しかったのかしら」
「どうしたんだい」
駅に向かう途中で、由美が何か疑問に思ったようだ。
「通説のように、家に居る妻を恋しく思いながら、旅から帰る途中の歌だと辻褄も合うのよね。ところが、お父さんの言うように旅に出かける時だとしたら、何を恋しく思いながら旅をしているのだろうということになるのよ」
「なるほどね。そうか、だから帰る途中の歌にしたのかな」
「結局、人麻呂に聞かなきゃ分からないのかしら」
「う~ん、謎が新たな謎を呼んでしまったよ」
恒之は、由美を明石駅の前で降ろし、帰路についた。
奈良、伊勢、明石と回ったが、古代史と万葉集にはまだまだ多くの謎があることを改めて実感した旅となった。
|




邪馬台国発見
Copyright (C) 2008 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.



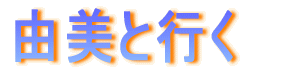
![]()

![]()
![]()