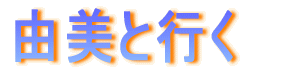|
5、
「中々おいしいよ」
「そう、良かった。外食が苦手なお父さんだから、ちょっと心配だったの」
「薄味でとてもいいよ」
恒之は、外食や売っている物の味付けが、どうにも好きに成れなかった。
それで、いつもはできるだけ家で食べるようにしている。
妻の洵子が留守をしている時は、自分で作る。
「そう言えば、お父さん」
「どうしたんだい」
「忘れていたけど、伊勢の話を聞きたいから私のアパートに来たんじゃなかったの」
「そうだ、そうだったよ。正倉院展の話から、思わず盛り上がってしまって、すっかり忘れていたよ」
「そう大層な話でもないんだけどね」
「そんなことないよ。お願いだから、知っている事を出来るだけ詳しく教えてくれよ」
「その教授も、余談だけどと言って話した程度だから、余り良くは覚えてないわよ」
「構わないよ」
「何でも伊勢からは、たくさんの水銀が採れていたみたい。当時、水銀はかなり重宝されていたそうなの」
「水銀がねえ」
「水銀と言ったら液体の物質を思い浮かべるけど、その頃は、朱色の染料や長寿の薬にもされたそうよ。だけど、一番の利用目的は金だったらしいの」
「金?」
「そう、金と混ぜるとアマルガムといった物質になり、それを火で熱すると水銀が蒸発して金だけが残るの。だから、金を抽出したり、金メッキをするのに水銀は欠かせなかったそうよ」
「なるほどねえ。となると、金を扱おうとしたら、同時に水銀も必要になるわけだ」
「そうなの。だから、金と同じくらい重要だったそうよ。それでね、驚いたのは、丹という地名がついている所は水銀を採っていた所で、丹は、水銀を意味するんだって」
「丹は、水銀を意味しているねえ。なるほど、そうなると地図だよ、地図が見たい」
「お店でそんなこと言っても無理よ」
「さあ、早く食べて帰ろう」
「お父さん、そんなに慌てなくても」
「そうか、丹がキーワードか」
二人は、早々に切り上げてアパートに戻った。
恒之は、早速に伊勢周辺の地図を広げていた。
「あるかなあ、丹のつく地名が」
「どうかなあ。江戸時代の頃までは、まだ採掘されていたそうよ」
「あったよ。ほら、ここに。丹生とある」
「丹を生産する場所。まさしく、水銀を産出していたという地名ね」
「そうか、ここで水銀を採っていたんだ」
恒之は、帰り道のコンビニで買った缶ビールを開けた。
「なるほどなあ」
「古くはね、不老不死の薬として珍重されたり、宗教的に使われたりもしたそうよ」
「薬って、水銀は中毒症状が出るんじゃないの」
「少量だとそうでもないらしいんだけど。量が多くなると幻覚を見たりするから、それが密教では神がかり的な雰囲気を作り出していたのかもね」
「なるほど、超現実の世界に入り込んだ気分になったのだろうか」
「だから、昔の修験道者が、険しい山の中へ入っていたのは、修行もあるのだろうけど水銀や鉱脈を探していたという説もあるそうよ」
「ほう、聞けば聞くほど興味が出てくる話だね」
「そして、その究極は、即身仏だって」
「なんだよ、それ」
「生きながらにして仏になっていくのよ。水銀を多量に服用すると、もちろん水銀中毒を起こすんだけど、それを続けると死んでも体が腐食しなくなるんだって」
「水銀漬けにしてしまうんだ」
「そう、だから幻覚を見ながら成仏し、ミイラ化するわけよ」
「なんだか、究極の密教だよなあ」
「つまり、服毒自殺よね」
「ちょっと怖い話だなあ」
冷たいビールのせいでもあるが、恒之は身震いしそうだった。
「常温で液体の金属でしょう。相当不思議な物質だと思われていたのでしょうね」
「長寿の秘薬、宗教、染色、金加工。幅広い使用先があったということは、相当珍重されただろうなあ」
「でしょうね。そうだわ」
そう言って、由美は立ち上がり、机の上から資料を出してきた。
「ほら、ここ」
由美が指し示す所には、東大寺の大仏の写真があった。
その横には、大仏鋳造に使われた物資や人員、食糧、雇賃などの統計資料が記されていた。
「ここに、水銀が五八六二〇両使われたとあるでしょう」
「本当だ。でも、それってどれくらいの量だろう。両じゃ分からないよ」
「ちょっと待ってね」
由美が別の資料を持ってきた。
「水銀が約二千二百キログラム、金は約四四〇キログラム使われたそうよ」
「ほう、二トンを超える水銀とは、それは確かにすごい量だよな。それが、大仏に金メッキをするために使われたというわけだ」
「それでも、江戸時代の頃までずっと採掘されていたということは、相当の埋蔵量だったのね」
「ということは、昔の伊勢は水銀で栄えたと言えるかもしれないなあ」
「そうね、採掘をするためには、多くの人の力が必要だったんでしょうね」
「そうか、伊勢と水銀か」
恒之は、缶ビールが効いてきたのか、次第に眠くなってきた。
「お父さん、コタツで寝ちゃだめよ」
だが、由美の声もだんだん遠くになっていった。
|




邪馬台国発見
Copyright (C) 2008 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.