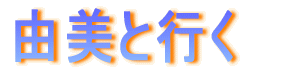|
4、
ちょうど日が暮れかかった頃、恒之は、由美のアパートに着いた。
「お父さんいらっしゃい」
「やあ、元気だったかい」
「私は大丈夫よ。それより、お父さんの方こそ、今年の秋は家の改装で大変だったみたいね」
「三十年振りの大改装だったよ。由美が正月に帰ったらびっくりするかもしれないよ」
「そう、それは楽しみね」
恒之が、由美のアパートに来るのは昨年の秋以来だった。
二階に上がるとコタツが出してあった。
「こちらも寒くなったみたいだな」
「昼はそうでもないけど、夜はちょっと冷えるのよね」
こたつに入り、恒之はほっと一息ついた。
「今日も、朝からよく走ったよ」
「そうだ、正倉院展はどうだったの?私も行きたかったんだけど、時間が全然取れなくて行けなかったの」
「昨年は、あまり聖武天皇に関わる展示が無かったけど、今年はもう満載だったよ。そうだ、ほら、これを見てごらん」
恒之は、荷物の中から、正倉院展の目録を出した。
そこには、今回の展示品が、大きな写真入りで紹介されていた。
「この螺鈿の鏡って本当に凄いわよね。こんなのよく作ったものね」
「そうだよなあ。この地球上に今ある鏡の中で、一番豪華かもしれないよ」
「それが、千数百年以上も前に作られたんだから驚きよね」
「技術と贅の限りを尽くしているよ」
由美は、感嘆の溜息を漏らしながらページをめくった。
「あっ、これが囲碁盤ね」
「そうだよ。これを見るのが、今回一番の目的だったんだよ」
「立派な囲碁盤ね。わあ、この碁石、象牙で造られているのね。それも一個々々染めた上に、鳥の模様が刻んであるんだって」
「本当に、超スーパー豪華だろう。だが、驚くべきは、そんな国宝級の囲碁盤がなぜ正倉院にあるのかということだよ」
「それは、聖武天皇の遺品だったからなんでしょう」
由美は、父が何を言おうとしているのかよく分からなかった。
「聖武天皇の遺品だったのは、間違いないだろう。じゃあ、どうやってそれを手に入れたんだろう。とても、当時のわが国で作られたとは考えられないよ」
「そうよね。きっと、遣唐使がもらってきたのよ。正倉院には、そういう物が多いと聞いたことがあるわ」
由美は、それが一番妥当な考え方だと思った。
「そうだね。確かに、それが正解かもしれない。だが、日本では遣唐使と言っているけど、所詮は唐への朝貢使だよ。そんな遠い島国からやってくる使節に、これだけの囲碁盤を持たせるなんてあり得ないよ」
「そうかなあ」
「この囲碁盤は、国王クラスの人でないと使えないほどの代物だよ。それを、囲碁を知っているかどうかも分からない使いの者にプレゼントなんかすると思うかい。どうかしたら、本当に、『猫に小判、豚に真珠』になってしまうよ」
「確かにそうかもねえ」
「当時の唐でも、これほどの囲碁盤は、そういくつもあったわけではないだろう。それを手放すとなると、そこには、相当の思い入れがあったとしか考えられないよ」
由美は、父の話ももっとものように思えた。
「では、どういうことなの」
「考えられることは、一つしかないよ。聖武天皇がもらってきたんだよ」
「聖武天皇が?」
「そう」
「聖武天皇が唐に行ったということ?」
「それしか、考えられないね」
「本当に?」
由美は、父の発想がにわかには信じられなかった。
「聖武天皇は、相当囲碁が強かったと言われているんだよ。これ以外にも三面ほど囲碁盤が残されているんだ。聖武天皇は、遣唐使として唐に渡り、当時まだ若かった玄宗皇帝と囲碁を打った。だが、かなり強かった聖武天皇は、殆ど指南役に近かった。そして、日本に戻ることになった聖武天皇に、玄宗皇帝は、手元にあった最高の囲碁盤を贈呈した。そういう説もあるんだよ」
「ふうん。本当かどうかよく分からないけど、でも、もっともらしいわね」
「聖武天皇は、たとえ朝貢使であっても、囲碁に関しては、若き日の玄宗皇帝にとっては大先生だった。そう考えると、あれだけの囲碁盤が正倉院にあるのも納得いくよ」
由美は、とってもそれらしい説であると思ったが、根本的なところでの疑問があった。
「ところでお父さん、聖武天皇は、本当に唐へ行ったの?」
今まで歴史を習ってきたが、聖武天皇が遣唐使で唐に行っていたなんて、由美は聞いたことがなかった。
「そうだよなあ。そんなこと普通言われてないものなあ。ええと、そう言えば資料を保存していたよな」
そう言って恒之は、パソコンを取り出した。
「やっぱり、パソコンを携帯しているんだ」
「デジカメのデータが一杯になったら、すぐにパソコンに移さないと、次の写真が撮れないからね。逆に、パソコンがあれば、限りなく撮影ができるんだよ」
そう言いながら、恒之は、保存データを呼び出していた。
「ここに、旧唐書と新唐書の一部があるんだけどね。まず、『旧唐書』の日本国伝に、長安三年朝臣真人が方物を貢献に来たと記されているんだ」
「つまり、遣唐使のことね」
「問題は、その後だよ。その真人は、冠を被り、紫の服で身を包み、腰には絹の帯をしていたとあるんだ」
「何かすごい出で立ちのようね」
「歴史書に記されるくらいだから、唐もきっと驚いたんだろうね。さあ、その次だよ。真人は、好く経書を読み、文章を理解し、容姿は穏やかで優美だったと書かれているんだよ」
「賢くて、容姿端麗ってことかしら。その真人って人、唐から大絶賛されているわね」
「唐も、相当立派に見えたんだろうね。則天武后が、隣徳殿に於ける宴で司膳卿を授けて帰国させたとあるんだよ」
「まるで国賓並みの厚遇ね」
「じゃあ、こちらの『新唐書』の方を見てごらん。大きくは変わらないんだけどね」
「同じようなことが書いてあるようね。あら、真人粟田とこちらでは書かれているわ」
「朝臣の真人粟田を遣わし、方物を貢献したと、ここで粟田という名前が出てくるんだよ。そして、真人はよく学び、巧みに文章を書き、動作には偉容があったと、同じように唐から絶賛を受けているんだ」
「唐からそこまで賞賛された人物がいたなんて驚きよね」
「あくまで朝貢使だから、普通は使者としか書かれないよ。前回行った使者にいたっては、不誠実で言うことが信用出来ないとまで書かれていることを考えたら、この真人粟田に対する待遇や記述は、異例中の異例なのかもしれない」
由美は、その資料を見ていたが、ふと目に付いたことがあった。
「ねえ、お父さん。この後に『粟田復朝』とあるけど、また行ったということなの?」
「そう、ここが一番肝心なところなんだ。何故また行ったのか。どうして粟田でなければならなかったのか。その後に書かれているのは、粟田が再び来朝し、諸儒に沿った経典を拝受したいと請うたとあるんだ。つまり、朝貢使として来たのではなく、様々な宗教についての教えを請い、経典をいただきたいというのがその目的だったというんだ」
「経典を求めて、はるばる唐へやってきましたということね。なんか西遊記みたいね」
「そう、その三蔵法師玄奘がインドの経典を漢訳した仏典も今回の正倉院展に出ていたよ。三蔵法師玄奘奉と記されていた。その目録にも載っているはずだよ」
由美は、先ほどの本を開いた。
すると終わりのほうに二ページにわたって写真と解説があった。
「本当ね。三蔵法師玄奘の名前や日付や場所まで書かれているわね」
「さらに驚くべきは、その解説によると正倉院の東南に聖語蔵というもうひとつの校倉があって、そこには約五千巻の経巻があるというんだよ」
「何なのそれ」
「正倉院だけでも驚愕の遺産にあふれているというのに、いわゆる古文書や経典が五千巻もあるんだよ」
「そんなの知らなかったわ。でも、どうしてそんなにたくさんあるの」
「さあ、そこなんだよ。粟田は、教えを請うたお礼に大きな幅の広い布を献じたとあるだろう。そこまではいいよ。その後だよ」
由美も、その資料に釘付けになった。
「あらゆる、賞、物、貿、書を持って帰るとあるんだ」
「ええっ、教えを請いに来たのに、お礼は大きな布で、帰る時にはあらゆる物を持って帰ったというの?」
「どこか変だろう。散々、教えを請いながら、そのお礼は布だけ。その挙句にあらゆる財宝や書物を持ち帰ったというんだよ。唐としては納得いかないよなあ。だから、書き方がさっきのあの絶賛とかなり違うんだよ」
「記す人もどうも納得いかないなあと思いながら書いたのかしら」
「『お前、どれだけ持って帰れば気が済むんだよ』というような声が聞こえてきそうだろう」
由美は、そこでハッと気づいた。
「ねえ、お父さん。もしかして、それが、正倉院や聖語蔵に残されているということなの」
「かなりの物は、きっとその時に唐から持ち帰った物ではないかと思えるんだよ。あくまで想像だけどね」
「でも、それって、一歩間違えば窃盗と思われてしまうかもしれないじゃない」
「確かにね。だから、真人粟田でなければ出来なかったことなんだよ。普通、あり得ない話だよ」
「どうして、真人粟田なら出来たの」
「一つには、やはり彼本人の偉大さにあったんだろう。唐から相当尊敬に値する人物と思われていたからね。もう一つは、真人粟田が唐へ行った年で分かったんだよ」
「開元初とあるわね」
「そう、それは玄宗皇帝が即位した翌年にあたるんだよ。つまり、玄宗が皇帝になり、年号も開元と改めて、唐が新たな船出をした年にあたるんだよ」
「玄宗皇帝が意気揚々としている時よね」
「そんな時に、ただ経典をくださいとだけ行く訳がないよ。きっと、即位のお祝に行ったんだよ。ましてや、知らない間柄ではないから尚更だよ」
「囲碁の大先生が、お祝いにわざわざ海を渡ってはるか日本からやってきてくれたとなると、玄宗皇帝も喜んだだろうね」
「まあ、囲碁だけではないだろうけどね。そうなると、経典が欲しい?結構、結構。他にも囲碁盤に始まって何でも持って帰りなさいと、部下にも指示を出した。皇帝の指示とあれば誰も口を出せないだろう」
「真人粟田も巧くやったわね」
「ここぞとばかりに、ごっそりと持ち帰ってしまった。そして、それが、遺品として正倉院や聖語蔵に保管された。これで辻褄がぴったり合うだろう」
「真人粟田が、後の聖武天皇だということね。真人粟田という人が、唐に行ったことに間違いはないだろうけど、でも、本当に後の聖武天皇なのかしら」
「憶測に過ぎないと言われたら、そうかもしれない。でも、真人というのは言ってみれば官位、その身分を表しているんだよ。それも、朝臣、宿祢、連、公とかいろいろあるんだけど、真人は、その最高位だそうだ。つまり、国王やそれに相当する地位にあるということなんだ」
「そうなの。だから、いくら玄宗皇帝が若い時だったとは言え、一緒に囲碁が打てたという訳ね」
「だろうね。囲碁がどれだけ強くても、一朝貢使とは打たないだろう。朝貢使の方も恐れ多くて打てないよ。聖武天皇は、倭国あるいは奴国の王族の末裔だから、十分過ぎるほど真人に相当する訳だよ」
「なるほどね」
「一番の確証となったのは、万葉集だよ」
「万葉集?」
「そう、唐から帰るときに詠った歌があるんだよ」
そう言って、恒之は袋から資料を取り出した。
「ほら、これだよ」
そこには、山上憶良の歌があった。
いざ子ども 早く日本へ 大伴の 三津の浜松 待ち恋ぬらむ
その横には、訳も書かれていた。
さあ皆の者よ 早く日本へ帰ろう 大伴の三津の浜松も さぞ待ちわびていよう
「山上憶良の歌とあるわね」
「つまり、この歌が、真人粟田つまり後の聖武天皇が、朝貢使としての役目を立派に終え、使節団のみんなに、さあ国へ帰ろうと号令をかけている歌だよ」
「やはり、山上憶良ではなく、聖武天皇なのね」
「真人という国王クラスの人がいる使節団でだよ。いざ子ども、つまり、さあ皆の者と号令をかけるんだよ。山上憶良とは、どんなに偉い人なんだよ。真人に対していざ子どもなんて、もし山上憶良がそんなふうに言える立場にあるとしたら、山上憶良はもう天皇だということになってしまうよ」
「そうよねえ」
「つまり、この歌を山上憶良が詠んだとしたら、山上憶良は、実は真人粟田であり、聖武天皇自身であったということだよ」
「聖武天皇は、いろんな名前を使っていたのかしらね」
「天皇になる前は、きっと、多くの名前を使ったんだろうね。あるいは、それぞれの分野で使い分けていたかもしれないよ」
「聖武天皇ってどんな人だったんだろう」
「きっと、当時のスーパーヒーローだったのかもね。唐の歴史書で絶賛されるような人物だし、日本でも、聖という字が名前に使われたくらいだから、相当賢かったんだろうね」
「ねえ、お父さん」
「何だい」
「おなかが空いた」
「そうだよなあ。しゃべっていたらもうこんな時間だよ。じゃあ、何か食べに行こう」
「やったあ、ねえ、この前、友達と食べに行って美味しかったお店があるのよ。そこに行ってみようよ」
「それいいねえ。よし、ではそこへ行ってみよう」
二人は、車に乗り、食事に出かけた。
|




邪馬台国発見
Copyright (C) 2008 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.
![]()

![]()
![]()
![]()

![]()
![]()