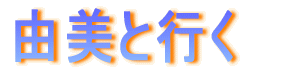| 12、
「徳川家康は、1603年、何に任じられて幕府を開いたのでしょうか」
「何だっけ、せい、せい、ええと思い出せないわ」
恒之が、台所に行くと、隣の居間で由美が明代に勉強を教えていた。
「こんな簡単なことが分からないようでは、ちょっと心配だわ」
「そうだ、将軍」
「将軍の前に何かつくでしょう」
「分かった、征夷大将軍」
「やっと出たわね。すぐに思い出せるように、教科書をもっと読むことね」
『征夷大将軍か。そう言えば、そういう勉強もしたなあ。んんっ、ちょっと待てよ』
恒之は、思い当たるところがあった。
『征夷大将軍は、平安朝の頃から始まっている。ということは、征夷とは…』
恒之は、居間に置いてあるパソコンを開いた。
「徳川幕府は、家康から始まって何代まで続いたのでしょうか」
二人は、まだ歴史の勉強を続けていた。
「ええとねえ、最後の将軍は慶喜だったよねえ。何代目だったかなあ」
「これくらいのことが分からないようでは、本当に心配してしまうわ」
「そんなのいちいち覚えてられないわよ」
「開き直ってどうするの。お父さんくらいの年になって忘れたっていうならまだ分からないでもないけど、受験生が忘れてしまうようでは困りものね」
恒之は、インターネットで検索したサイトの画面を見ていた。
「慶喜かい、徳川第十五代将軍だよ」
「ええっ、すごい、お父さんまだ覚えていたんだ」
明代が、驚いていた。
「どうだ。まだまだ、捨てたもんじゃないだろう」
「お父さんは、今でもまだ覚えているというのに、明代が思い出せないようでは、かなり危ないわよ」
「大丈夫。今日の昼に行った初詣で、しっかりお願いしておいたからね」
昨年は、熊野大社まで行ったが、今年は、近くの神社へ初詣に出かけた。
「困った時の神頼みじゃねえ。それに、明代は、おみくじを引いていたけど、どうだったかしら」
「末吉よ」
「ほら、その神頼みでも末吉でしょう」
「末吉なんて嫌だから、もう一回引いたけど、やっぱり末吉だったわ。それに、勉強運の所を見たら『努力せよ』だって。もう、去年と一緒なのよ」
「その通りじゃない。神様もよく見ているわね。とにかく自分が頑張るしかないのよ」
「分かっているわよ」
「本当に、大丈夫かしら」
由美は、ちょっと明代を持て余し気味だった。
「ああっ、そうか。そういうことなんだ」
恒之が、パソコンに向かって何か言っている。
「お父さん、どうしたの?」
由美が明代を相手するのに飽きたようで、恒之の側にやってきた。
「大変だ。凄いことが見えてきたよ」
「どんなことが?」
「聞きたい?」
「長くならない程度ならね」
「じゃあ、これを見てごらん」
恒之は、最初のサイトを画面に出した。
「これは、先ほど話していた歴代の征夷大将軍のリストだよ」
「征夷大将軍ってこんなにもいたのね」
「そうなんだ。さっき見て、お父さんも驚いたよ」
「最後は、徳川慶喜なのね」
「徳川家は、十五人とも征夷大将軍だよ」
「お父さん、慶喜が十五代だと分かったのは、これを見ていたからなのね」
「実は、そうだったんだ。慶喜が徳川何代将軍かまでは、中々覚えていないよ」
「普通、そうよね」
「そんなことより、問題は、この征夷大将軍が、いつ頃から始まったかなんだよ」
由美は、そのリストの最初を見た。
「794年に始まっているわ」
「その年とは?」
「鳴くよウグイス平安京」
明代が、大きな声で答えていた。
「そうよね。明代ちゃんもこれくらいは、すぐに分からないとね」
「つまり、征夷大将軍は、桓武天皇の頃に始まり、途中空白の時期もあったようだけど慶喜の頃まで続いたわけだよ」
「平安京へ遷都した年に、東北を攻めていたのね」
「2代目征夷大将軍は、坂上田村麻呂だ」
「名前は聞いたことあるよね」
「でもこの征夷とは、『夷』を征伐するということだろう」
「そう、かな」
「じゃあ、その『夷』は、平安京からわざわざ征伐に行かなければいけないほど、どんな悪いことをしたというんだろう」
「そんなの知らないわ」
「攻撃を仕掛けてきていたとか、なんか相当敵対的なことがなければ、あんな遠い所まで兵を送ることはないよ。でも、そんな話は聞いたこと無いだろう」
「無いわね、知らないだけかしら」
「どちらにしても、当時、桓武天皇あるいは朝廷にとって、その『夷』が最大の脅威だったということになるんだ」
「最大の脅威?」
「征夷大将軍を任命してまで、『夷』を攻撃した。そして、それは、たとえ途中に空白があったとしても、幕末まで続いたんだよ」
「かなり長期よね」
「幕末までそれが続いたということは、いつも対策をしておかなければいけないということだろう。そうなるとだよ、『夷』は、根本的に朝廷と敵対関係にあったということになるんだよ」
「そこまで、朝廷が恐れる『夷』って何かしら」
「そうなんだ。『夷』とはいったい何か。朝廷は、『夷』を、どうしてそこまでマークし続けたのか。ここには、この国の大きな謎が秘められているように思えるよ」
「なんだろうね」
「由美、この『夷』の文字を見て、何か思い出さないか」
「『夷』の文字で?」
「そう」
「何かしら」
由美は、父に言われてその字を見つめた。
「あっ、万葉集のあの歌にあったわ」
「そう、人麻呂が、旅の途中、明石海峡まで来て詠ったあの歌に出てくるんだ。『天離る鄙(ひな)の長路ゆ恋来れば』の鄙は、原文では『夷』となっている」
「その『夷』と関係あるの?」
「無関係ではないだろう。『夷』は、他にも何首か出てくる。つまり、万葉集で『夷』が普通に詠われているということは、まだその頃は、特に問題は無かった。そうなると、『夷』が朝廷と敵対関係に変わったのは、やはり『征夷大将軍』が作られた桓武朝になってからということになるよ」
「そうね」
「となると、平城京から平安京に移る時期に、歴史を変えるほどの大きな異変が起きていたことが考えられる」
「どんな?」
「昨年の初詣で、熊野大社に行っただろう」
「行ったわね」
「その時、熊野大社は、別名『日本火之出初之社(ひのもとひのでぞめのやしろ)』と呼ばれているということだったよな」
「そうね」
「『ひな』と呼ばれていた出雲の中心が、『ひなもと』つまり『日本』だよ。そこから、相当大きな集団が本州最北に集団移住して、そこも『ひな』と呼ばれていた」
「移住?」
「そう、ただし望んで移住したのではなく、むしろ逃避したと言った方が正しいかもしれない」
「逃避って、何から?」
「それは、桓武朝からの攻撃を逃れるためだよ」
「桓武朝からの攻撃?」
「藤原氏や桓武天皇は、出雲を征服し、抵抗する人たちを武力で容赦なく制圧した」
「その抵抗した人たちが、東北に逃れたというのね」
「そういうことだよ。だから、いつまでも執拗に抑圧されたわけだよ」
「でも、本当にそうかしら」
「青森で『日本中央』と記された石碑が発見されたり、津軽を、以前は『東日流』と表現していたとか、その痕跡が今にも残されているんだよ」
「東日流?」
「つまり、東に日(ひな)が流れてきたということかな。地名には歴史が残されているからね。『夷』を元は、『日』と書いていたのかもしれない」
「なるほどね」
「最も残されているのは、言葉だよ。出雲と津軽の言葉に共通するのは?」
「ズーズー弁?」
「そう。たとえば、少数が移動しても、移動先の言葉に同化してしまうよな。その子どもとかになると、もう、そこの地域の言葉にしっかりなじんでしまう」
「そうね、私もかなり向こうの言葉に影響されてきているわ」
「だから、相当多くの人が出雲から移動したんだろう。そして、個々の表現においては異なるものの、イントネーション、訛りはずっと残ってきたんだよ」
「そうかもしれないわね」
「かなり前のことなんだけど、紀伊半島にある新宮市出身の人と話をしたことがあるんだ。それも、ほんの立ち話程度なんだよ。ところが、その人は、急に驚いたように『お前、新宮の出身か、俺も新宮だよ』と言ったんだ」
「新宮市出身の人に言われたの?」
「そう。言葉が似ていたらしいんだよ」
「じゃあ、相当似ていたのね」
「それは、よく分からないんだけど、その人は、出雲大社と熊野本宮大社の関係かなあと言っていたよ。確かに、当時、人の交流があったことは考えられる」
「言葉は生き物とも言うけど、訛りは中々取れないよね」
「そう言えば、津軽弁では、『などさ』『わゆさ』だけで、会話になっていると聞いたことがあるよ」
「それだけで?」
「そう」
「どういう意味なの?」
「『などさ』は、何処へ行くんだ。『わゆさ』は、風呂へ行くところだという意味だそうだ」
「まるで暗号みたいね」
「そういうことだよ」
「え?」
「つまり、津軽は、いつ何処に朝廷からのスパイが潜んでいるか分からないといった状況にあったんだよ。だから、他所から来た人間に聞き取られないように、暗号みたいな言葉になっていったそうだ」
「それを考えたら、大変な生活だったんだろうなあと思えてくるわね」
「都からの抑圧に怯えながら生きていたということが言葉にも残されているわけだよ」
「なるほどね」
「さて、そうなると、桓武天皇の頃に歴史がどう変えられたのか、そしてそれは何故なのかという所が問題になってくる」
「あまりに、難しすぎるわ」
「そうだよなあ。しかし、そのために、出雲の人たちは大変な目に会ったわけだよ。そういうことすら歴史には残されていない」
「でも、どうやって調べるの?」
「それは、古事記や日本書紀を見れば必ずそういった歴史は、きっと何らかの形で痕跡が残されているよ」
「じゃあ、これからは、万葉集だけでなく古事記や日本書紀も調べるということ?」
「そういうことかな」
「ええっ、それは大変なことよ」
「いつかは、そうなると思っていたよ。まあ、また図書館に行ってみるよ」
「ほどほどにね」
「そんな大層なことでもないよ。本を読むだけのことだよ。由美のようにテストがある訳じゃないし、気楽に始めてみるよ」
「そう、頑張ってね」
その頃、側で勉強していた明代は、こたつで寝てしまっていた。
「明代ちゃん、ほら起きなさい。風邪ひくわよ」
「は~い」
明代は、由美に起こされて二階に上がった。
恒之も、パソコンの電源を切り、風呂に入ることにした。
今年も、新年早々から古代史に没頭する恒之だった。
|




邪馬台国発見
Copyright (C) 2008 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.