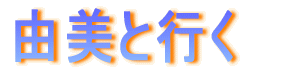|
10、
「ただいま」
「あっ、お姉ちゃんお帰り」
「お帰りなさい。今日は遅くなったのね」
洵子と明代が、由美を出迎えていた。
「同級生が数名で集まるって言うから、倉吉でちょっとゆっくりしていたのよ。あら、お父さんただいま」
「お帰り、連絡すれば迎えに行ったのに」
「大丈夫よ。ああ~、家の中が変わってる~」
「だから、言っただろう。帰ったら驚くよって」
「台所も綺麗になって、奥の部屋が洋室に変わっているじゃない」
「お母さんがね、こんなふうにしてって、お父さんにお願いしたのよ」
「素敵な居間になったのね。以前、どうなっていたのか思い出せないわ」
「まあ、ゆっくりしていてね」
洵子が、台所へ行った。
「お母さん、夕食はいいわよ。友達と食べてきたから」
「それは、聞いていたから用意してないわよ。お茶くらい入れてあげようと思ってね」
「ありがとう」
洋室の一部に畳が三畳ほど敷いてあり、そこにコタツが出ていた。
由美は、早速足を入れた。
「やっぱり、冬はコタツが一番よね」
「お姉ちゃん、私、将来は看護師さんに成ろうと思うの」
「そう」
「冬休み明けに模試があってね。それで成績が良かったら、看護科のある高校に推薦してもらえるかもしれないの」
「じゃあ、頑張らないと」
「だから、冬休みは、最後の追い込みよ。分からないところがあったら教えてね」
「いいわよ」
「じゃあ、上がって勉強してくるわね」
そう言って、明代は二階へ上がった。
「お待たせ。お茶が入ったわよ。お父さんもどうぞ。あらっ、明代は?」
「勉強するって、二階に上がったわ」
「そう、本当にどうなるか心配で、心配で」
「でも、頑張っているみたいじゃない」
「最近になって、いよいよお尻に火がついただけよ」
「でも、塾でバイトしていると全然やる気のない生徒も結構いるのよ」
「じゃあ、何のために塾へ行ってるのよ」
「親が行けと言うから行っているんだろうけど、やる気のない子どもを塾に入れてもどうかと思うわね」
「親にしてみれば、藁をもすがるような思いじゃないの」
「塾や家庭教師なんて、そんな親の弱みに付け込んでいるようなものよ。そこで、バイトをしていて言うのもなんだけど」
「まあ、結局は本人の努力だと、分かってはいるんだけどね」
「やる子は、塾に行っても行かなくてもやるし、やらない子は、塾に行ってもやらないわ」
「でもね、つらい親の気持ちも分かってあげてね」
「それは、もういろいろ言われるもの。特に家庭教師は大変よ。子どもの出来が悪いのは、まるで家庭教師のせいだみたいに言う親もいるのよ。確かにお金をいただいて教えには行くよ。ところが、成績が悪ければ家庭教師の教え方が悪い。成績が良ければ、子どもが頑張ったから。何か嫌になっちゃうわ」
由美は、ちょっと嫌な思いもしているようだった。
「由美に、塾や家庭教師のバイトを勧めたのは、お父さんだよ。前にも話したけど、由美が学校の先生になりたいと言うから、それなら人に教えるということがどういうことか、少しでも実際にその経験をした方がいいかもしれないと思って勧めたんだ」
「分かっているわよ。でも、結構楽しいこともあるのよ」
「そうか、あまり無理にすることもないんだよ」
「大丈夫よ。休みの時なんか、集中講義が入ったりするでしょう。そうなると、バイト料もたくさん貰えて助かっちゃうわ」
「それは、いいね」
恒之は、由美の笑顔を見ていると、本当にうれしくなるのであった。
「ところで、お父さん。人麻呂の歌の謎が解けたんだって?」
「そうよ、そうよ。この前ね、お母さんの話から大事なヒントを得たって言いながら、教えてもくれないのよ。まあ、お母さんが聞いても分からないのかもしれないけどね」
洵子が、横で由美と一緒にお茶を飲みながら話している。
「そうか。じゃあ、資料を取ってくるよ」
恒之は、由美と万葉集や古代史のことについて話をするのが、一番の楽しみだった。
二階に置いていた資料を手にすると、すぐに下に降りた。
「由美と人麻呂の旅の歌八首を見て、実際明石海峡まで行っただろう。そして、七首目はやっぱり西を向いて詠んだ歌だと、そういう結論になったよなあ」
「そうだったね」
「ところが、そうなると新たな疑問が出てきた。由美が言ったように、では、『恋ひ来れば』が、家で待つ妻を思いながらではないとしたら、人麻呂は、いったい何を、あるいは誰を恋しく思いながら、この歌を詠ったのかという新たな疑問が生まれる。そういうことだったよね」
「そうよ」
「あれから、ずっと考えていたんだけど、よく分からなくて。お父さん、今、PTAの広報部の役員をしているだろう。先日、編集会議の後で、『人麻呂は、石見を詠った歌もいくつか残してますよね』って担当の先生から、聞いたんだよ」
「そうね、石見を詠った歌は、確かにあったわね」
「それが、これだよ」
恒之は、人麻呂が、国司の任期を終えて、石見を離れる時の歌を由美に見せた。
由美は、しばらくそれを見ていた。
「ねえ、由美ちゃん、それ読んで分かるの?」
「現代文約も書いてあるから、何とかね」
「そう、よく分かるわね」
「人麻呂が、涙ながらにこの歌を詠った気持ちが分かるだろう」
「そうね」
「お父さんったらね、お母さんにこの歌の説明をしながら、涙を流しているのよ。もう気分は、人麻呂に成りきっているんだから」
恒之は、この歌の話をすると、今でも涙が出てきそうになる。
「では、この二首の違いが分かるかい」
「違いって?」
「この二つの歌は、違う人のことを歌っているんだよ」
「そうなの。どちらも、残してきた妻のことを詠んでいるのかと思ったわ。そう書いてあったわよ」
「そう、解釈ではね。でも、よく読んでごらん。二首と言うからには、違うことを詠っているはずなんだよ」
「何処が違うんだろう」
由美は、その二首をもう一度見比べた。
「あれっ、ここに『児』ってあるけど、これは子どもを意味するんじゃないかしら」
「そうだよ、この二つの歌は、彼女と子どもを置いて旅立つ人麻呂の悲痛な思いを詠っているんだよ」
「なるほどね。子どもまでいたら、確かにつらかっただろうね」
「もう、聞くも涙、語るも涙の物語といったら、こういうことを言うんだよ」
恒之は、ちょっとウルウルきそうだった。
「それは分かったけど、旅の歌の謎が解けたと言っていたのは、どういうこと?」
「由美の言っていた、人麻呂に聞けということだったんだよ。人麻呂は、それを語っていた。つまり、この歌の後日談が、あの旅の歌なんだよ」
「後日談が無いかと言ったのは、お母さんだからね」
横で洵子が、得意そうに話している。
「お母さんの言葉で、あの旅の歌が浮かんできたんだよ」
「ね、そうでしょう」
「だから、後年、石見へ置いてきたその二人に会いに行く時の歌が、あの八首だと考えられるんだよ。第二巻に別れの歌、そして第三巻に再会を恋焦がれる旅の歌だよ」
「なるほどねえ。愛しい彼女と、あの時小さかった子どもの成長した姿が、もうすぐ見れるかと思うと、それはうれしくてたまらなかったでしょうね」
「早く、一刻も早く会いたいという人麻呂の思いが、あの一連の歌と『恋ひ来れば』に表現されている。これが、お父さんの言っていた謎解きの結論だよ。どうだい、これですっきりしただろう」
恒之は、もう完璧すぎて胸を張らんばかりだった。
「お父さん、実は、私ね」
「な、何だい」
これ以上、もう何も無いと思っていたので、恒之はちょっと戸惑った。
「お父さんの後日談という解釈は、すばらしいと思うわ」
「そ、そうか」
「私が変に思ったのは、どうして七首目だけが東を向いた旅の終わりの歌として解釈されているかということだったの」
「そうだよ。その通りだよ」
「私ね、原文も含めてあれからよく読んでみたの。するとね、『大和島見ゆ』と読まれているんだけど。原文では、『倭嶋所見』なのよね。倭嶋、倭なのよね。原文では、『大和』じゃないのよ」
「うん、そうだった」
「倭は、倭国であって、大和とは違うじゃない。ではどうして、倭を大和と読んでいるんだろうと思って、大学で調べてみたのよ」
「それで、どうだった」
「『倭文』とか織物の名前として使われた歌以外、つまり地名として使われた『倭』は、すべて『大和』と解釈されていたの」
「そうなのか」
「それでね、じゃあ、原文で『大和』と表現されているのは、どれくらいあるのか調べてみたのよ」
「調べたら?」
恒之は、ちょっとドキドキしてきた。
「原文で、地名として『大和』という文字が使われている歌は一首も無いの」
「ええっ!」
恒之は、あまりのことに驚いてしまった。
万葉集には、九州の地を詠っている歌が多いとは思っていた。
しかし、聖武天皇は、奈良にもいたのだから、大和の地を詠った歌も多いはずである。
「『大和』という地名の入った歌が一首も無いなんて、どういうことなんだろう」
「もっと凄いのはね」
「まだ、何かあるのかい」
「原文で、『日本』と書いてあるのを何と読んでいると思う?」
「まさか、大和」
「そのまさかよ。私が調べた限りでは、原文に『日本』と出てくるのは十七首ほどあるのよね。その内一首を除いて、他全部が『大和』と解釈されているの」
「なんだよ、それ」
「その一首も『日本』と漢字で書いてはあるけれど、小さく横に『やまと』とルビがふってあるのよね」
「つまりは、原文にある『日本』は、すべて『やまと』と読ませているということかい」
「そうなの」
「ところが、原文には『大和』と書かれている歌は、一首も無いんだろう」
「そうなのよ。何か変でしょう」
「どういうことなんだ」
「他にも『夜麻登』とか『山跡』、『也麻等』など『やまと』と読めるところは、当然のごとく『大和』と書かれているわ」
「『やまと』と読める地名、『倭』、『日本』これらはみな『やまと』あるいは『大和』ということかい。原文には『大和』という地名は、一切出て来ないというのに」
「あくまで、私が調べた範囲内でということよ」
「これは、たまたまではないよ。そういう意思でもって『大和』にしている」
「それも、かなり強引な意思よ」
「だよなあ、その意図はなんだろう」
「なんでしょうね」
二人の今の認識では、その解答と思われる考えは出て来なかった。
どうしようもなく、頭を抱えるしかなかった。
「謎が解けたと思ったのに、とんでもない強力な謎が出現してしまったよ」
「そうね」
その横で、洵子は、二人の話について行けず、居眠りをしていた。
恒之も由美も、今夜は、もう寝るしかなかった。
|




邪馬台国発見
Copyright (C) 2008 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.