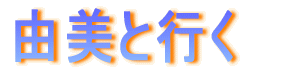|
25、
「お母さん、明日、昼過ぎの特急で帰るね」
「そう。寂しくなっちゃうわね」
由美と洵子が居間で話している横で、恒之は、パソコンに向かって中国の史書について調べていた。
「そういうことかなあ」
恒之が、つぶやきながらパソコンの画面を見ていると、由美が横にやってきた。
「何か分かった?」
「少しずつだけど、概略は掴めてきたよ」
由美は、恒之の手元に置かれている宋書を見たが、やはり理解できそうになかった。
「高句麗に好太王の残した石碑があることは知っているだろう」
「好太王碑ね」
「その文中に、もともと百済や新羅は、高句麗に貢物を持ってきていたとあるんだ。そこへ、391年に倭が海を渡ってやってきて、百済や新羅を征服した。それに対し高句麗の好太王は、396年、水軍を率いて百済を攻め、百済は高句麗の家臣となることを誓ったとある。ところが、399年、百済は、その誓いを破り倭と手を結んでしまった。そして、その翌年400年には、倭人が攻めてきたので、5万の歩兵・騎兵をつかわして新羅を助けた。そういったようなことが書かれているんだ」
「内容まではよく知らなかったわ」
「4世紀末、アジア東北部には高句麗、この列島には倭、それに挟まれるように百済や新羅などの国があり、覇権争いをしていたようだ」
「ふうん」
「宋書には、好太王碑に書かれている頃より少し後の事が、記されているようだ」
「なるほどね。これで、なんとなく背景が掴めたわね」
「いろいろ調べてみると、この宋書には、今まで知らなかったようなすごい事が書かれているよ」
「どんなことが?」
「宋書には、421年から478年にかけて、讃、珍、濟、興、武、いわゆる倭の五王と云われている王の事が記されているんだ」
「今までの史書とは、ちょっと違うのね」
「過去の史書にあったようなことは、一切出てこない。この5王についてだけしか書かれていないよ」
「そうなの」
「それぞれの王で少し名称が違うものの、彼らは、『使持節、都督、倭、百済、新羅、任那、加羅、秦韓、慕韓七國諸軍事、安東大将軍、倭国王』と称していたということだ」
「何なの、それ?」
「彼らは、この列島だけでなく、朝鮮半島をも含めて、その勢力下にしていたようだよ。そして、宋の皇帝から、それらの称号を得ていたみたいだ」
「朝鮮半島までも勢力下にしていたとなると、相当大きな力を誇っていたことになるわよ」
「安東大将軍ということは、中国より東は制覇していると言っているようなものだ」
「大帝国と言った様相ね。でも、好太王碑にあった高句麗は、入ってないわね」
「そう、つまり、諸軍事、安東大将軍というのは、朝鮮半島制覇、そして対高句麗のためとも考えられるんだよ」
「高句麗との戦いは、続いていたのね」
「そこで、あのよく解らなかった倭王武の上表文だが、解説があったので、概略は掴めたよ」
「そう。どういうことだったの」
「まずは自らの説明をしている。『倭は、中国から遠くにあり、自分の祖先は、自ら甲冑を身につけ、山や川を駆け巡った。そして、東は毛人を征すること55カ国、西は衆夷を服すること66カ国、渡って海北を平定すること95カ国と国土を広げてきた』。このように、列島と朝鮮半島を制覇していると、当時の状況を述べているんだよ」
「勢力を大きくしたと言っているのね」
「ところが、高句麗も大きな力を持っていたようだ。『私は、祖先から引き継いで貢物を届ける船を百済から皇帝の所へ送ろうとするも、高句麗が行く手を阻んでいます。もし、皇帝のお力で強敵高句麗をくじき、方難を靖んぜば、尚一層皇帝に忠節を尽くします』。これが、この上表文の概略かな」
「つまり、高句麗を倒すためにお力をお貸しくださいということね」
「簡単に言えばそういうことだろう」
「でも、倭王は、相当大きな勢力を誇っていたと考えられるわね」
「国内はもとより、半島まで勢力下に置くとなると、その兵力はかなりのものだったんだろう」
「まず、人員からすると、好太王碑に高句麗が5万人を派兵したとあったから、倭王もそれくらいは送っていたのかもね」
「正確には分からないが、それに近い数字だったかもしれない」
「当時の人口を考えると、各地から総動員されたと考えられるわね」
「そして、そこには大量の武器が必要になる。ということは、製鉄を制していた勢力でなければ出来ないことだよ」
「ええっ、この列島で製鉄を制していた勢力ということは…」
「そして、その倭王とは…」
「い・ず・も」
「そうだよ、そこに行き着くよ。彼らは、3世紀頃、この列島にやってきて、『山川を跋渉し』、国内の各地で製鉄産業を盛んにしたんだ。そして、国内を統一すると共に、吉備などで武器や数々の鉄製品を生み出し、4世紀から5世紀にかけて、朝鮮半島まで勢力を伸ばしていた。その広範囲な移動を可能にした機動力と言ったら、それは馬だよ」
「製鉄と馬ね」
「そこに君臨していたのが、きっと大倭王なんだよ。そして、その大倭王のいる所が、臺(台)であり、中国の史書に出てくる『邪馬臺(台)国』ということだよ」
「お父さん、繋がってきたね」
「倭の5王とは、おそらく出雲勢力の大倭王と考えて間違いないだろう。彼らは、漢字の文化圏からやって来ていたから、当たり前だが、漢字も巧みに使えたという訳だ」
「何かよく分からなかった歴史の謎が、少し解けてきた気がするわ」
「でも、そう簡単でもないよ。まあ、この後の史書も見ることにしようか」
「そうね。この後が、どう描かれているかしら」
「宋書の次は、6世紀頃に書かれた『南斉書』だが、ここには数行しか登場しないよ。その中にも、倭王武は、鎮東大将軍と称していたとある」
「やはり、大きな勢力を誇っていたのね」
「その次になると、唐代に入るよ。まず、『梁書』が636年に完成している。これも、今までの史書を参考にしているようだ。その次は、648年に完成したとされる『晋書』だよ。こちらも同様に過去の文献を参考にしている程度かな。その中で、倭人は、自ら呉の太伯の末裔だと言っているよ」
「3国時代の呉からも、多くの人が流れて来たのかしら」
「それで呉服が伝えられたということなのかな」
「そういう文化が残るくらいだから、相当たくさんの人々が来たのね」
「さて、次は『隋書』だよ。同じく唐代に完成している。656年ということだから、かなり新しい資料と言えるだろう」
「そうね」
由美は、また新たな史実が書かれていることに期待をした。
「これは、中々面白いよ」
「どんな事が書かれているの?」
「基本的には、過去の資料を参考にしているようだが、まあ見てごらん」
由美も、その隋書を見た。
倭國在百濟、新羅東南、水陸三千里、於大海之中依山島而居、魏時、譯通中國。三十餘國、皆自稱王。夷人不知里數、但計以日。其國境東西五月行、南北三月行、各至於海。其地勢東高西下。都於邪靡堆、則魏志所謂邪馬臺者也。
「同じようでも、ちょっと違うわね」
「おそらくいろいろな資料を持っていたんだろう。ところが、この中にはとても重要なことが書かれているよ」
「夷人とあるね」
「そう、今まで倭人はあったが、夷人は出て来なかったよ。そして、夷人は、里数を知らず、日を以って計っているとある」
「そうね」
「ということはだよ。家の中で生活している人が長さを計る場合、例えば手とか物を使って、その何倍かというように計るよな」
「そうかな」
「日数を数える時は別にして、そういう人は、長さを日で計らない。つまり、夷人と言われる人達は、何日かかるかを基本とするような生活パターンだったことになるよ」
「そういうことね」
「あそこまで10日だ、20日だとその距離を考えるということは、それだけ広いエリアを移動していたということだ。だから、その国の境界を、東西が5百日、南北が3百日と表している。そして、その国は東が高くて西が低いとも言っている」
「結構広いよね」
「そして、それぞれが、海に出る。ということは、この夷人の言う国とは、東は関東地方から西は九州までその勢力下にしていたことになる。宋書に出てきた、倭王武の書簡にあったような範囲だよ」
「そうね。そうなると東西南北が海に出ることになるね」
「関東から中部のあたりは非常に高地だよ。そして、中国地方から九州に至ると低くなる」
「ぴったりだね」
「さて、じゃあその基準としている場所は何処なのかということになる」
「基準って?」
「つまり、東は高くて西は低いという基準だよ。例えば、九州に居る人が考えたとしてごらん。西には海があり、東に行くに従って高くなりますと表現するだろう。関東の方を中心にして表現したらその逆となる」
「まあ、そう言われたらそうかな」
「ということはだよ。その基準として考えられている地点はその中心ということだよ」
「中心ねえ」
「中心にある国。つまり、中つ国だよ」
「ええっ、中つ国って古事記に出てくる葦原中国のこと?」
「やはりここで言う倭國は、出雲の国のことを指しているんだよ」
「まあ、確かに宋書から出雲がクローズアップは、されたけどね」
「この列島を支配下に置き、日で距離を計る必要がある国と言えば、倭の五王から続く出雲系の国しかあり得ないだろう。そして、その基準となる本、中心が日の本で、日本となったのだろうか」
「どうなんだろうね。じゃあ、その次を見てみましょうよ」
「そうだね。その倭國の都は、邪馬堆にあった。『魏志で言う所の邪馬臺(台)なる者なり』、つまり、大倭王の居る所が邪馬臺(台)だということだよ」
「それは、後漢書にもあったわね」
「おおっ。その次は、いよいよ、倭国の王が登場してきたよ」
由美も、思わずその文章に見入った。
「開皇20年(600)に、その王が隋の皇帝に使者を送ったとあるよ。王の名前は、姓が阿毎、字が多利思比弧。号が阿輩き彌、おおきみと呼ばれていたということかな。その使者が、皇帝に問われていろいろ答えているよ」
「どんなこと?」
「これは、大変な内容だよ。『王は、天を以って兄と為し、日を以って弟となす』とあるよ。そして、日の出の前から座り、日が出ると『我弟に委ねん』と言うそうだ」
「天が兄で、日が弟ということ?」
「ひょっとして、これは、天照大神と須佐之男命を意味しているのかもしれないよ」
「でも、天照大神は、女性だったよね」
「元々、天照大神は男性の神で、月読命が女性の神だったように思えるんだよ」
「そうかなあ」
「須佐之男命が、伊耶那岐命に追い払われて天上界へ向かう場面があっただろう」
「あったわね」
「その時に天照大神が、須佐之男命を迎え撃つ様子を覚えているかい。天照大御神は、弟神が国を奪いに来ると思い、髪をみずらに結い、八尺の玉を髪や左右の手に巻き、千本の矢と弓を振りたて、地面に足が埋まるほど蹴散らかして、『何故に来たる』と叫ぶんだよ。これは、どうみても兄の姿だろう」
「解釈では、男装したとあるけどね」
「それに、天の岩戸の前で女性の神が裸になって踊るんだよ。そんなこと女性の神の前でする訳ないだろう。須佐之男命と一緒に怒られるだけだよ」
「そうかもね」
「つまり、天照大神は、元々は兄という設定の話だったのではないだろうか」
「出雲では、そういう話が伝えられていたのではないかと言いたいのね」
「それに、『阿毎多利思比弧』は、『あめのたりしひこ』と読まれているようだけど、『あまてらすひこ』と、読めないこともないんだ。まあ、続きを読もうか。その後は、王の妻や太子、官職名、風俗について書かれているよ。あっ、これは…」
「どうしたの?」
「大業3年(607)に送った国書だよ」
「国書?」
「そう、ほら。聞いた事があるだろう」
由美は、恒之が指し示す所を見た。
國書曰「日出處天子致書日没處天子無恙」云云。
「あっ、これね。皇帝が見て怒ったという国書ね」
「『日出ずる處の天子、書を日没する處の天子に致す。恙無きや云云』なんて堂々と書かれたら皇帝も驚いただろう。天子は、この世で自分1人だけのはずだと、皇帝も怒っているよ。『蠻夷の書無禮なる者有り。復た以って聞するなかれ』とあるよ」
「かなり怒っているようね」
「これは、逆鱗に触れたかな。歴史書に記録されるくらいだから、並の怒り方ではなさそうだ。でも、翌年、倭国に使者を送っているよ」
「様子を伺いに行ったのかしら」
「本当の所は、兵を送って滅ぼしてしまいたいくらいだろう。天子が2人いるなんて、あり得ないことだよ。また、どちらの国も交流が無かったのでお互いよく分からないといった様子が伺えるよ」
「すると、詳しく調べるための使者だったのかもしれないわよ」
「だからかどうか分からないけど、道のりも記されているよ。どの国か特定できるようにしたのだろうか。そうだ、それをたどれば、その大倭王のいる邪馬臺(台)國に行けるよ」
「そうよね」
「文林郎裴清が使者で、百済から竹島、耽羅国、対馬国、そして一支国を経て筑紫国に到達している」
「ここまでは、今までと変わらないわね」
「九州の筑紫国から東に行くと秦王国があったそうだ」
「東のどこだろうね」
「小倉のあたりか、宇佐、あるいは、下関のあたりだろうか。中国人のようだとも言っている。王国なんて言うくらいだから、結構大きい国だったのかなあ。北九州か海峡を渡ったあたりなんだろうな。ええっ、これはどういうことなんだろう」
「どうしたの?」
そこには、『又經十餘國、達於海岸』とあった。
「秦王国から、また十余国経たら、海岸に達したということね」
「十余国、今で言えば十幾つの都市を経たら海に出た。ということはだよ。海に出たと表現したのは、それまでは陸地を行っていたんだろうなあ」
「でしょうね。海の見えないところから海の見える所へ出たということよね」
「これは、中国山脈を越えたということだよ」
「中国山脈を越えたの?」
「瀬戸内海に沿って東へ行くと、海は見え隠れするだろう。『海岸に出たよ』という思いをしたのは、険しい山地を抜けて海の見える所へ出たからだよ」
「なるほどね」
「出雲街道とか、広島街道とか古い街道が今にも残っているよ。人麻呂が石見の国司を終えて都に帰る時、中国山脈を越えて広島に抜けているようだ。石見と広島は、距離的にも一番山脈を超え易いルートだったみたいだよ。出雲へ抜ける街道もあったようだ」
「この頃から道があったのかもね」
「いや、もっと古くからあったかもしれない」
「で、それからどうしたのかしら」
「すごい歓迎ぶりだ。倭王の使者が数百人を従えて出迎えているよ。何か場所が設営されて、鼓角が鳴らされているようだよ」
「まるで、歓迎の記念式典ね。峠越え、お疲れ様。そして、ようこそ倭国へということかしら」
「その後も大変だよ。10日ほどしたら、また使者が来ているようだけど、2百余騎で出迎えているよ。やはり、これは出雲の騎馬隊だよ」
「それも、大騎馬隊よ」
「戦力を鼓舞しているのかな。騎馬民族たる出雲らしいけど、ちょっと、それは逆に脅威と思わせてしまったかもしれないよ。何と言っても、中国は匈奴や鮮卑など北方騎馬民族に手を焼いて万里の長城を築いたくらいだから。『邪馬』という文字を使ったところにも、その思いが表れているよ」
「大騎馬隊は、ちょっと怖いかもね」
「そこから都に行き、早速、王と会見をしているよ。倭王は、大いに悦んだとある」
2人は、その後に書かれている倭王の言葉に見入った。
「我聞海西有大隋、禮義之國、故遣朝貢。我夷人、僻在海隅、不聞禮義、是以稽留境内、不即相見。今故清道飾館、以待大使、冀聞大國惟新之化」
「海の西に礼儀の国、大隋国があると聞いて朝貢したと言っているよ。これは、おそらくあの国書の事を言ってるんだろう」
「きっとね」
「自分は夷人だとも言っているよ」
「この隋書の初めにも夷人とあったわ」
「海の隅に僻在していて、礼儀も聞けず、中々会うこともできなかったと、ちょっと言い訳っぽいなあ。やはり、国書のことで皇帝が怒っているということが、伝わったのかな。でも、海の隅に僻在とは、出雲大社のあるあたりを表現するにはぴったりとした言葉だよ」
「そうよね」
「そして、今、道を清めて建物も飾って大使をお持ちしておりましたと、かなり謙虚に話しているようだ。そして、最後に、大國惟新の化を聞きたいと言っているみたいだ。つまり、大国をどう刷新するのかを聞いているってことだろうか」
「大国維新の化?」
「この倭王は、隋との関係がかなり悪化していると思っているみたいだ。だから、大国維新の化、大国を一新させたいがどうしたら良いかと聞いたということではないだろうか」
「大国を一新ねえ」
「きっと自らを大国と言っていたんだよ」
「大国?」
「大国主命だよ。大国の主、それが大倭王ということではないかな」
「そうかなあ」
「そうだ。ちょっと待って」
そう言って、恒之は席を立った。
しばらくして、冊子を片手に戻ってきた。
「ほら、ここを見てごらん」
それは、昨年の正月、熊野大社へ行った時に買った本だった。
「熊野大社の石灯篭に神紋があるだろう」
「あっ、大の文字だわ」
「熊野大社の中にある、本殿、拝殿、伊邪那美神社、稲田神社。あらゆるところに『大』という神紋が見えるだろう」
「本当だわ。あちこちに付けられている提灯にもみな『大』の文字があるわ」
「大国の象徴が残されていると思わないかい」
「まあねえ」
「こっちを見てごらん」
由美は、恒之がパソコンの画面を指し示すので、そちらを見た。
「これは、隋書みたいね」
「よく読んでごらん」
「隋書では、倭国の文字が、倭ではない?」
「そう、今までの史書では、みな倭とか、倭人、倭国とあった。ところが、この隋書では、倭の文字が、人偏に妥という字が使われているんだよ」
そこには、原文の写真もあった。
「人偏は同じだけど、委のところが妥になっているわ」
「この文字は、パソコンにも無い文字なんだよ」
「ええっ。でも、簡単な文字よ」
「30画を超える難しい文字はあっても、この人偏に妥の文字は無い」
「どうしてかしら」
「さあ、それは分からない。では、どうしてその文字が使われているかだよ。倭国のことを伝えるんだから倭国と今まで通り書いておけば、別にいいと思うんだよ」
「そうよね」
「ということは、この国が、今までの倭国ではないと中国が認識していたと言う事なのかもしれない。そして、国名も倭国ではなかったとも考えられる。つまり、大国と呼んでいたということではないだろうか」
「じゃあ、大国と書けばいいじゃない」
「ところが、自分を天子だなんて言うとんでもない国王がいるんだよ。もう、皇帝は激怒している。その上、国名は大国で、行ってみたら騎馬民族だよ。大という文字なんか絶対に使えるかとなったように思えるんだ。それで、通常使わないような文字を、その国名の文字にあてたと考えられないだろうか」
「では、どうして、その文字なの?」
「妥を何て読む?」
「妥協の妥だから『だ』よね」
「人偏は、『い』と読むだろう。合わせると?」
「『だい』?」
「ただ、この文字は、『たい』と読まれているんだよ。だが、出雲弁の世界では、その聞き分けができたかどうか分からない。倭国と大国を合わせて表現しようとしたのかもしれない。まあ、想像でしかないけどね。でも、大国と呼んでいたとは思うよ。大国の山で、大山だよ」
「大山の名前の由来が、大国から来ているというの?」
「ただ単に大きい山だからというだけではないように思えるよ。出雲の国名には、大、臺(台)、堆、そして人偏に妥と、『だい』あるいは『たい』という語音がからんでいるんだよな。さて、その国王が聞いた事に、使者の清が答えているよ」
皇帝徳並二儀、澤流四海、以王慕化、故遣行人來此宣諭
「皇帝の徳について述べているようだけど、難しいよ。そして、館に就き、人を遣わして、また述べている」
朝命既達、請即戒塗
「どういうことかしら」
「最後は自分で言わずに人を通して言っている。朝命は、既に達した。即刻、塗を戒めることを要請する。どうも、相当怒っている雰囲気だよ」
「そうかなあ」
「やはり、大国と自らを呼んでいるのが気に入らなかったのかな。朝廷の命は下った。即刻戒めよ。塗は、何だろう。塗ると言えば看板。つまり、大国という名前や、自らを天子とする態度など一切の塗り替えをしろというようなことだろうか」
「そうだとしたら、最後通告的言葉みたいね」
「その後、宴亨を設け、さらに使者や方物も携えて、丁重にお見送りはしたとはある」
「とりあえずは、お帰りいただいたようね」
「そして、この隋書にある最後の文字だ」
由美は、その文字を見た。
此後遂絶
「此の後、遂に絶つ。これが、この訪問の結果のようだ。遂に絶つとは、国交を断絶したということかな」
「それは、大変なことになってしまったわね」
「大倭王が、あまりにも大きな力を誇っていたということだろうか。この国では偉大だったんだが、中国と対等に渡り合おうとしたために、関係を悪化させてしまったということかもしれない。所詮は、大陸から見たら、大海の中、山島に依りて居を為している国邑に過ぎないということだよ」
「あの国書が、まずかったのかしら」
「天子を名乗るのは、どちらにしても、刺激が強すぎたかな」
「そうかもしれないわね。でも、国交断絶というようなことになって、この後どうなるのかしら」
「ところが、隋は、この10年後には滅んでしまうんだよ」
「ええっ、そんなに早く隋が滅んでしまったの」
「隋は、短命だったからね。そして、次に誕生したのが唐だよ。この唐が、わが国に与えた影響は計り知れないものがあるよ」
「ということは、その唐と、どういう付き合いをしたかということになってくるわね」
「そういうことだよ。それは、この後の史書に書かれているのかもしれない」
「ねえ、お父さん、そろそろお風呂に入っていいかしら。もう眠たくなってきたわ」
「そうだな。旧唐書や新唐書もあるが、また別の機会にということにしようか」
由美は風呂へ、恒之はパソコンの電源を落として二階へ上がった。
そして、今までの所を振り返りながら、その日を終えた。
|