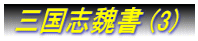 卑彌呼以死、大作冢、徑百餘歩、[扁犬旁旬]葬者奴婢百餘人。更立男王、國中不服、更相誅殺、當時殺千餘人。復立卑彌呼宗女壹與、年十三爲王、國中遂定。 卑弥呼以て死す。大きな冢を作る。徑百余歩、徇葬する者、奴婢百余人。更に男王を立てしも、國中服せず。更相誅殺し、当時千余人を殺す。また卑彌呼の宗女壹與、年十三爲るを立てて王となし、國中遂に定まる。 卑弥呼が亡くなり、大きな塚、つまりは墓が造られたとあります。先に、女王国は、宮崎県の西都原に存在したと述べました。では、その西都原には、それに相当する古墳があるのでしょうか。 西都原台地には、巨大古墳群があったことにも触れました。 そこは、300基以上もの古墳のある全国有数の大古墳群です。そのうち、9割が円墳で、その中には、わが国最大の円墳があります。その円墳には、わずかに方墳部分がついているので帆立貝式古墳とも呼ばれていて、円墳部分の直径は、132メートルもあります。 まさに、この列島の女王に相応しい墓です。しかし、現地では、そういった認識はなく、男狭穂塚(おさほづか)古墳と呼ばれています。そのすぐ横には、寄り添うようにしてこれまた九州最大の前方後円墳があり、こちらは女狭穂塚(めさほづか)古墳と呼ばれています。 この男狭穂塚古墳こそが、卑弥呼の墓に相当します。その横の女狭穂塚古墳は、卑弥呼の娘であるところの市杵島姫、あるいは壱與の墓だとも考えられます。 ただ、ここで、最初に疑問となったのは、女王に相応しいとは言え、直径が百余歩とありますから、そうなりますと、1歩が1メートル以上になってしまいます。いくら大股だったとしても、1メートル以上は少々無理があります。そこで、調べてみますと、魏国の度量基準では、基準となる足を左右どちらかに決め、その足の歩数で計測していたことが分かりました。 つまり、今でいう2歩が、この魏書における1歩ということになります。大人の1歩がおよそ60㎝あまりといったところですから、当時の1歩が120数cmです。まさしく、その男狭穂塚古墳は、百余歩で、ぴったりと合います。 卑弥呼が居たのは、南九州でしかあり得ません。そのエリアの中で、大きな拠点があり、この記述に合う古墳は他には見当たりません。この男狭穂塚古墳こそが、卑弥呼の墓であり、同時に、西都原こそが女王国『邪馬壹国』のあった地ということになります。 しかし、それは、決して『邪馬台国』ではありません。 政等以檄告喩壹與、 壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人送政等還。因詣臺、獻上男女生口三十人、貢白珠五千、孔青大句珠二枚異文雜 錦二十匹。 政等、檄を以て壹與を告喩す。 壹與、倭の大夫率善中郎将掖邪狗等二十人を遣わし、政等の還るを送らしむ。因って臺に詣り、男女生口三十人を献上し、白珠五千孔、青大勾珠二牧、異文雑錦二十匹を貢す 卑弥呼が亡くなったので、男王を立てたが、抗争が起き、壹與を女王としたら治まったと、ありました。 その壹與は、魏の使者が還るにあたり、使者20人を同行させています。その使者は、魏国で、『臺』に詣でて貢物を献上したとあります。これで、所謂魏志倭人伝は終わりです。 この最後の部分に『邪馬台国』を理解する上での重要な記述があります。つまり、次の女王となったのは、壹與とあります。そして、その壹與の使者は、『臺』に詣でたとあります。 ここなのです。当たり前ですが、『壹』と『臺』が、明確に使い分けられています。 よくある議論の中で、中国の史書に『壹』と『臺』の書き間違いがあるとか、写し間違いがあるというようなことが言われることがあります。それは、まずあり得ないことです。 何故なら、臺とは皇帝のいるところを意味しているのです。中央官庁、皇居、総理官邸、ホワイトハウスといったその国の最高権力者のいるところを『臺』としているのです。 東京の文字を棟京とか、凍京などと文部科学省の研究者が書き間違えるに相当するほど、あり得ないことです。一般の人でも、そんな間違いをすることなんかありません。 つまり、邪馬台国の『台』とは、『臺』です。邪馬台国とは、この列島の皇帝に相当する王がいる所を意味しています。 では、卑弥呼が女王だからそこが邪馬台国ではないのか。そのように、理解されているのが一般的というか、殆どがそういう解釈ではないでしょうか。 ところが、そうではないのです。卑弥呼は、あくまで邪馬壹国の女王であり、皇帝のいるところである邪馬台国の女王という表現は魏志倭人伝の中の何処にもありません。 |