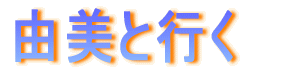|
36、
「冷えた麦茶があったよねえ」
「コーヒーも冷やしてあるよ」
「あっ、それがいいな。お父さんも飲む?」
「じゃあ、いただこうかな」
由美は、2人分のコーヒーをグラスに入れてきた。
恒之は、いつもドリップ式で出したコーヒーをボトルに入れて冷やしている。
「楽しい出雲旅行になったね」
「玲子さんが、一緒だったから良かったよ。彼女、中々勉強熱心だね」
「何でも、卒論のテーマは、藤原氏についてらしいわよ」
「ほう、それは、かなり古代史の本質をついているねえ」
「だから、今、唐の歴史を研究しているそうよ」
「なるほどなあ。唐の勢力だから、まず唐について調べるという訳だ。すばらしい。ところで、由美は、卒論のテーマはどうするんだい」
「まだ、来年のことだから分からないけど、やはり、万葉集と古代史とのかかわりみたいなところを考えてはいるのよ」
「面白そうだね」
「万葉集に出雲がどう描かれているのかが、当面のテーマかな。古事記や日本書紀も関係してくるから、ちょっと大変なのよね」
「それは、お父さんも興味深いところだよ」
「でしょう」
「で、今はどんなことを調べているのかな」
恒之は、由美がどんなことに興味を持っているのか聞きたくなった。
「記紀の重要な役割は、出雲対策にあるでしょう。そう考えると、神武東征と言われているんだけど、神武が日向から出発して宇佐、筑紫、安芸、吉備などに逗留しながら進んでいくでしょう」
「そうだね。結構何年も立ち寄っているんだよなあ」
「それは、当時、出雲の勢力の重要な拠点を、神武つまりは藤原の勢力が征服しながら進んだことを意味しているのかもしれないのよね」
「なるほど。表敬訪問だとそんなに何年も寄り道なんかしないで、さっさと紀伊半島をめざすよなあ。征服に要した期間というわけだ」
「そう考えられるでしょう」
「となると、まず宇佐に寄っているよ。宇佐も出雲の拠点だったということか。そういえば、須佐之男尊が九州を制圧した時の前線基地が宇佐神宮の場所だという説もあったよ」
「宇佐神宮が?」
由美は、コーヒーの入っているグラスを横に置き、パソコンを開いて宇佐神宮を検索した。
「お父さん、ほら宇佐神宮の神紋が三巴と五七の桐よ」
「やはり、そうか」
「宇佐神宮は、一之御殿、二之御殿、三之御殿とあるんだって。つまり本殿のことね。3人奉られているということなのかな」
恒之もその画面を見た。
「祭神は?」
「一之御殿が応神天皇、二之御殿が比売大神、三之御殿が神功皇后となっているみたいね」
「なるほど、藤原氏に征服されているよ。一之御殿は、八幡大神ともある。二之御殿は、市杵嶋姫命・湍津姫命・田霧姫命の3女神が奉られているとある。そして三之御殿に皇后が奉られている。二之御殿に奉られている3女神は、須佐之男尊と卑弥呼の間に産まれているから、宇佐神宮は須佐之男尊と卑弥呼、そしてその娘達が奉られていたのだろう。つまり、出雲の王と九州の女王が結ばれて娘が誕生し、宇佐神宮に奉られたということだよ」
「ということは、宇佐神宮は、天神と地神が統合した象徴のようなものじゃない」
「かもしれないよ」
「宇佐神宮は、全国4万社ほどある八幡宮の総本宮とあるでしょう」
「そうだね」
「その全国にある八幡神社は、須佐之男尊と卑弥呼、そして3女神を奉っているということなのかしら」
「当初は、おそらくそうだっただろう。だが、藤原平安朝以後がどうなったかは、分からないよ。当時は、前方後円墳のように、全国各地で出雲と九州が統合した倭国の象徴として、盛大に奉られていたと思われるよ」
「だから、神武天皇も最初に宇佐へ立ち寄ったということなのね」
「紀伊半島以上に重要な拠点だったと思うよ」
「次は、筑紫国へ行ってるわ」
「筑紫国と言えば、築前国一宮の宗像大社だよ」
「宗像3女神ね」
由美は、そう言いながら宗像大社のサイトを画面に出した。
「宗像市田島の辺津宮に主祭神である市杵嶋姫が、沖の島の沖津宮に田心姫が、そして大島の中津宮に湍津姫が奉られているわ。この3社を合わせて宗像大社と言うのね」
「ほら、その3女神は宇佐に降臨とあるだろう。やはり、宇佐で生まれているようだ」
「この3社は、博多湾から大陸と結ぶ航路に沿うように位置しているわね」
「沖の島は、ちょうど朝鮮半島に向かう玄界灘の中央にあるよ」
「この島からは、鏡、勾玉、金製の指輪など、約12万点もの宝物が見つかったそうよ。航路の安全を祈願してお供えしたのかしら。『海の正倉院』とも言われているんだって」
「んん?」
恒之は、表示されている地図を見ながらふと思った。
「どうしたの?」
「玄海灘の西に壱岐島があるだろう」
「中国の史書にもよく登場したわね」
「壱岐は、『いき』と読まれているよなあ」
「そうね」
「その壱岐島は、『いちきしま』とも読めるよ」
「読めないこともないわね。あっ、宗像大社の祭神は市杵嶋姫、『いちきしま』よ」
「三国志の魏書には、壱岐が一大国として出てきていたよ。一は、邪馬壹(一)の一。大は、出雲の大国の大。それが統合した一大国ということかな。そして、出雲と九州の統合の象徴たる市杵嶋姫命。一は、市杵嶋姫命の市に由来しているようにも思えるよ」
「なるほどね」
「その一大国の官職名に、卑奴母離とあるんだよ。つまり、出雲の夷、あるいは日のひなかな。そして、母離は守。日守といったところだろうか」
「筑紫国も出雲の影響下にあったということみたいね」
「そうだね。そして、次に立ち寄った安芸には、安芸国一宮の厳島神社がある。ここにも3女神が奉られていて、厳島は市杵嶋姫命にその名前が由来しているよ」
「瀬戸内海での安全な航海を祈願したのかしら」
「次の吉備にしても、備前国一宮の石上布都魂神社は、奈良の石上神宮に奉られている布都魂という、須佐之男尊が八岐大蛇を切った剣が祭神だった。今は、須佐之男尊が祭神だそうだ」
「お父さん、神紋は、三巴と五三の桐よ」
「やはり、言われるところの神武東征とは、藤原氏に出雲の拠点が征服されたことを意味しているのかもしれないよ」
「そうね」
「となると、日向は、どうなんだろう。高天原からニニギの尊が天降ったことになっているようだが」
「日向国ね」
由美は、日向国の神社を検索した。
日向国一宮は、都農(つの)神社とあった。
「お父さん、これ見て!」
そのサイトを見て由美が驚いたように言った。
「何が?」
「都農神社の神紋が丸に一なのよ」
「ええっ、一だって!」
「祭神は、大己貴命、大国主命よ」
「日向国一宮に大国主命が奉られていて、神紋が一とは驚きだよ。なんと言っても一は、邪馬壹(一)国を意味するからなあ」
「でも、一宮の一なのかもしれないわよ。ちょっと調べてみるね」
周辺諸国の一宮を調べてみたが、一といった神紋はどこにもなかった。
一宮以外にも、神紋に一を使用している神社は見つからなかった。
「都農神社以外に神紋が一という神社は無いということかしら」
「ということは、やはり邪馬壹(一)国を意味しているんだろう。すると、出雲の熊野大社が大、そして、日向国の都農神社が一で、大と一が揃ったことになるよ」
「そうね。その都農神社の近くに都萬(つま)神社とあるわ。字が似ているけど、何か関わりがあるのかしら」
「さあ、どうなんだろう。祭神は?」
「木花咲耶姫命よ」
「女性の神だ。木花咲耶姫命と言えば、日向に天降ったニニギの尊の妻だよ。妻?」
「お父さん、この神社の名前はつまよ」
「都農神社に都萬神社。由美、読み方を変えたら、『殿の神社に、妻の神社』だよ。出雲の殿に日向の妻ということになる。ここにも、出雲と九州の融合が奉られている。そして、都萬神社の祭神が藤原氏によって変えられていたとしたら、木花咲耶姫命ではなく別の祭神だったということになる。ええっ、すると、都萬神社は、出雲の殿に対する妻が奉られていたんだよ。それが誰かと言えば…、もう、あの人以外にはないだろう。これは、大変なことだよ」
恒之は、とうとう突き止めたように思い、胸が高まった。
「お父さん、都萬神社の地名は、西都市妻よ。地名までが妻よ」
「西都市と言えば古墳群があったよなあ」
「西都原遺跡ね」
「そこだ。そこにあるはずだ」
「何が?」
「墓だよ」
「誰の?」
「都萬神社に奉られていた女神の墓だよ」
「木花咲耶姫命?」
「何言ってるんだよ。卑弥呼だよ」
「卑弥呼の?」
「そう」
「卑弥呼の墓が、西都原遺跡に?」
由美は、恒之の言葉に驚いてしまった。
「さあ、とにかく調べてみよう」
「そ、そうね」
由美は、西都原古墳群について検索を始めた。
いくつかあったが、その中から、とあるサイトを画面に出すと、西都原遺跡について説明がされていた。
西都市街地の西に西都原と呼ばれている台地がある。その台地を中心に、311基の古墳が分布し、前方後円墳32基・方墳1基・円墳278基で構成されている。
「そのほとんどは円墳だ」
「そうみたいね。やはり、九州は円墳が中心だったようね」
そして、その台地の中央に、巨大古墳が2基あるとあった。
男狭穂(おさほ)塚と女狭穂(めさほ)塚と名前が付けられていた。
男狭穂塚は、2重の周溝を有する墳長約148メートルの特殊な帆立貝式古墳で、国内最大の円墳ともあった。
女狭穂塚は、墳長176メートルの楯型の周溝を有する前方後円墳で、九州随一の規模を誇っているとあった。
恒之は、すぐに魏志倭人伝にあった卑弥呼の墓についての記載が思い出された。
「卑弥呼が亡くなった時、大きな塚をつくり、その大きさは経百余歩とあったよ」
「そうだったね」
「ということは、男狭穂塚と言われているが、これが卑弥呼の墓だよ」
「ええっ、これが、卑弥呼の墓なの?」
「日向にあって、近くには都萬神社がある。その規模といい、場所といい、間違いないだろう」
「もし、本当にこの墓だとしたら、大発見よ」
「帆立貝式古墳とあるが、ほぼ円墳だ。それに、二重の周溝まで施してある」
恒之は、鼓動の高鳴りを感じた。
さらに、この2つの墓について調べた。
ところが、一部の古墳は調査されてはいるが、この2つの古墳も含め西都原遺跡の実体はあまりよく分かっていないとあった。
「そんなには調査がされていないということなんだろうか」
「どうしてかしら」
恒之は、こんなにも巨大で歴史的に貴重と思える古墳が、どうして調査されていないのか不思議に思えた。
すると、すぐにその疑問を納得させる記述が恒之の目に入った。
「なるほど。彼らは、その古墳の主が誰かを知っているよ」
「ええっ、どういうこと?」
「その巨大な2つの古墳は、木の柵で囲われていて、宮内庁の管理下で調査どころか立ち入りすら禁止されているとあるだろう」
「立ち入り禁止?」
「明らかにされたら都合が悪いと自ら言っているようなものだよ」
「都合が?」
「これが卑弥呼の墓だと判明してごらん。奈良に卑弥呼の墓もあり、邪馬台国もあったという説が、根底から崩れるだろう。唐、そして藤原氏の勢力は、ここが卑弥呼の墓だと知っているはずだよ」
恒之は、自らの考えの正しさが証明されたように思えた。
「由美、とうとう、卑弥呼の墓にたどり着いたよ」
「そうだといいね。ところで、その横にある大きな前方後円墳は誰の墓なんだろうね。結構大きいよ。九州で随一の大きさだということだけど」
「その円墳に寄り添うようにあるだろう。八重垣神社で天照大御神、つまり卑弥呼に寄り添うようにしていたのは誰だった?」
「市杵嶋姫命よ」
「おそらく、その市杵嶋姫命だろう。母と娘がそこに眠っているということだよ。なるほど。ということは、日御碕神社もそういうことだったんだよ」
「日御碕神社?」
「玲子さんが、日御碕神社にある日沈宮の祭神は、天照大御神ではなく卑弥呼だと言っていただろう」
「そうだったわね」
「その神社の向かいにウミネコの繁殖地になっている御厳島があっただろう」
「あっ、そうか。御厳島ということは、市杵嶋姫命よね」
「そうなんだよ。つまり、日御碕神社には、須佐之男尊、卑弥呼、市杵嶋姫命が奉られていたということなんだよ」
「ちょっと待って」
由美は、日御碕神社のサイトを開いた。
「神の宮には、須佐之男尊と3女神が奉られているわ。日沈宮は、天照大御神と五男神よ」
「なるほど、古事記で、須佐之男尊と天照大御神がうけいをした時に、須佐之男尊には3人の娘が、天照大御神には5人の息子が産まれたとあっただろう。藤原氏に征服されて祭神が変えられているよ」
「そうみたいね」
「神紋は、3つ柏だよ。須佐之男尊と卑弥呼、市杵嶋姫命を意味しているのだろう」
そして、須佐之男尊が、「吾が神魂はこの葉の止まる所に住まん」と、柏の葉を投げて占ったところ、日御碕神社背後の丘に止まったという伝承も紹介されていた。
「そうすると、あの前方後円墳は、やはり市杵嶋姫命なのかもね。卑弥呼と市杵嶋姫命は、各地で奉られているのね。その割に、中国の史書には卑弥呼は出てきたけど市杵嶋姫命は登場しなかったわね」
「いや、ちゃんと描かれているよ」
「ええっ、本当に」
「つまり、壹與がそうではないかな。壹與の壹は、市杵嶋姫命の市。つまり、一だよ。卑弥呼が亡くなって壹與が女王になったら争いが治まったとあっただろう。須佐之男尊と卑弥呼の娘、つまり、出雲と九州の統合の象徴である市杵嶋姫命であったからこそ、その争いを収拾させることができたと考えられないかい」
「なるほどねえ。そう言われれば、そうかな」
「そして、壹與が亡くなった時は、その出雲と九州の統合の象徴たる前方後円墳という形で墓が作られた。すなわち、前方後円墳の第一号だったのかもしれないよ。卑弥呼は、なんと言っても九州の女王だから、円墳だよ。申し訳程度に出雲を意味する方墳がつけられて、帆立貝式古墳と言われている。壹與、つまり、各地で奉られている須佐之男尊と卑弥呼の娘、市杵嶋姫命の墓が女狭穂塚だろう」
「でも、本当にそうかしら」
「おそらく間違いないよ。三国志魏書、所謂、魏史倭人伝に魏から使者が来ていたとあったのは、この西都原台地だよ。つまりここに、女王国と記されていた邪馬壹(一)国があったんだよ。もちろん、邪馬臺(台)国ではないよ」
「お父さん、どうしよう。卑弥呼や壹與の墓まで分かってしまったわよ。でも、魏志倭人伝に径百余歩とあったけど、男狭穂塚の墳長は148メートルよ。1歩が1メートル以上というのは長すぎないかしら」
「お父さんも、それが気になって今調べていたんだが、ここにあったよ。ほら、見てごらん」
由美は、父が指し示している画面を見た。
「今のわが国では、とにかく足を踏み出すのを1歩としているだろう。ところが、今もそうかどうかは分からないが、当時の中国では計測する足を右か左かを決めて、その基準となる足で歩数を計っていたとあるんだよ。つまり、今の日本で言うところの2歩が当時の1歩ということになるんだ」
「じゃあ、半歩が約60センチとしたら、1歩はおよそ120センチくらいということね」
「墳長148メートルから方墳の部分を除いて、円墳の直径が130メートルくらだとしたら、ほら、ちょうど百余歩となるよ」
「そうね。やはり、間違いなさそうね」
「卑弥呼は、おそらく、日向の地に眠っているだろうとは思っていたが、これで、ほぼ確定することができたよ。」
この間の古代史探索で、邪馬台国や卑弥呼の墓を解明できたであろうことに間違いないものと恒之は確信した。
『んん?』
恒之は、その時、ふとある事が思い浮かんだ。
「唐により、卑弥呼は天照大御神とされ、そして新唐書にもあったが、壹(一)與は臺(台)與にされてしまった。そして、臺(台)與とは、とよ、つまり豊だ。天照大御神と、豊だよ。それは、伊勢神宮だ!」
恒之は、伊勢神宮のサイトを検索した。
「伊勢神宮がどうしたの?」
「内宮、つまり皇大神宮には、天照大御神が奉られている。外宮は、豊受大神宮で豊受大御神が奉られている。豊とは、つまり、臺(台)與、それは、すなわち壹(一)與、市杵嶋姫命を意味することになるよ。ええっ、じゃあ、藤原氏に征服される前、伊勢神宮には、卑弥呼とその娘が奉られていたのかもしれないよ。ここも卑弥呼と市杵嶋姫命だよ。ということは、伊勢とは、卑弥呼と市杵嶋姫命を意味する?」
「どういうこと?」
「難しいよ。とにかく難しい」
恒之には、それ以上の事は分かりようも無かった。
伊勢神宮に秘められた謎は、底知れないようにも感じられた。
画面を見ると、伊勢神宮の神紋は、花菱であった。
菱形の四弁の花であるが、唐花菱とも唐花とも呼ばれていて、大陸伝来の文様である。
唐の最も強力な支配の下に置かれたのが伊勢神宮だと、その神紋が語っているように恒之には思えた。
そして、恒之は、グラスに残っていたコーヒーを飲み干し、その場に少し横になった。
とりあえず、古代史における最大の謎とも言われてきた卑弥呼の墓が自分なりに特定はできたが、果てしのない古代史の謎に、恒之はどこか放心状態にも近かった。
「お父さん、九州へ行こう」
「何だって」
「卑弥呼の墓を見に行こうよ」
「もう、特定できたからいいじゃないか」
「だめよ。やっぱり、自分の目で確かめないと」
「ええ~、宮崎まで行くって、大変だよ」
「もうすぐ、お母さんの実家に行くでしょう。その時に、九州へ行くのよ」
妻洵子の実家は山口県で、年に1回は里帰りをすることになっている。
「そうか、じゃあ、頑張って行ってみようか」
「そうしよう。やったあ、卑弥呼の墓見学ツアーよ」
「どうせ行くなら、帰りに宇佐神宮や宗像大社にも寄ってみようか」
「それって、神武東征と同じコースよ」
「そうだなあ。厳島神社や石上布都魂神社にも寄ったら、まったく神武東征と一緒だよ」
「お父さん、この際だからそこにも寄って神武東征体験ツアーにしようよ」
「そうだなあ。そうしようか」
「じゃあ、私、もう少し詳しく日程を考えるね。そうだ、お母さんにもいつ実家に帰るか相談しないといけないし、宿泊するホテルにも予約を入れないと。わあ、忙しいけど、楽しいことになったわ」
由美は、立ち上がり、洵子を探しに行った。
恒之は、これで古代史探求も一段落したように思えた。
『いろいろ謎だったことが解明できたようにも思えるが、同じように考えている人が他にもいないかなあ。そうだと心強いが、どうだろう。また、インターネットや図書館で調べてみるか』
確かに、万葉集や出雲には、まだまだ謎がひしめいている。
その一方で、由美や玲子がどういった研究をして卒論にまとめるか、それを期待しているのも一つの楽しみだ。
そして、石見や出雲国庁跡など、まだ見ておく必要のある場所も残っている。
『また、涼しくなったら観光がてら出かけることにしよう』
夏の昼下がり、居間で横になっている恒之の耳には、蝉の声が鳴り響いていた。
だが、暦の上ではもう秋だ。
その恒之に、ある万葉集の歌が浮かんできた。
君待つと 我が恋ひをれば 我が宿の 簾(すだれ)動かし 秋の風吹く
額田王の歌だった。
『額田王とは、どんな人だったのだろう。実在の人物だったのか。はたまた、聖武天皇の手による登場人物だったのか』
恒之の万葉集に対する探求心は衰えることはなさそうだったが、窓から入ってくる心地よい風に、次第と眠りの世界へまどろんでいくのであった。
―完
|




邪馬台国発見
Copyright (C) 2008 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.