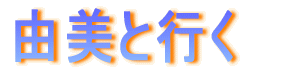|
30、
暑いほどの陽気にあふれた日も出てくるようになったが、雨の降る日はまだまだ寒々しい。
そんな日の夕暮れ時、恒之は、走行中の車のライトを点灯させた。
この時間帯の車は、みな帰りを急いでいるので要注意だ。
その時、そばに置いていた携帯電話にメールの着信音がした。
由美からのメールだった。
最近は、由美とのメールのやり取りがめっきり減っていた。
『めずらしいな。どうしたんだろう』
恒之は、信号待ちでメールを開いた。
【今年度は、3回生ということで日本史を専攻することにしました。ゼミは、古代史です。玲子も一緒です。5月の連休には、帰ります】
『そうか、連休には帰ってくるのか。それは楽しみだ』
玲子とは、由美と一緒にコーラスをしている友人で、以前、万葉集は個人集ではないかと貴重な意見をくれたことがあった。
恒之は、家に着くと早速洵子にも伝えた。
「そう、帰って来るの。良かった、また賑やかになるわね。明代にも教えてあげようかな」
洵子は、居間のパソコンから明代の携帯電話にメールを送っていた。
明代は、高校の看護科に進学したが、通学が大変だということで寮に入った。
洵子と2人だけの少し寂しい日々が続いていたが、連休は家族がみな揃うことになりそうだ。
恒之も由美に返信を送り、正月に隋書までで終わっていた中国の史書の検討を再開することにした。
わが国に残されている歴史に関わる資料では、古代日本の実像をつかむことはかなり困難であった。
そこで、中国の史書を調べることにしたが、その中で、出雲王朝の存在が浮び上がってきた。
所謂、邪馬台国については、壹(一)と臺(台)の文字の類似性、そして、その表す意味の根本的相違を認識することが、邪馬台国を理解する上では重要であった。
そして、邪馬という文字が使われているように、中国には、北方騎馬民族に対する相容れない思いが根底にあるようだ。
さらに、その邪馬臺(台)国であるところの大国が、つまり出雲王朝が、隋に自らを天子と称する国書を送ったため、中国皇帝の逆鱗に触れ、両国間の関係が一気に悪化することとなった。
隋の使者が大国の王と接見したが、関係の修復には至らず、国交が断絶した。
恒之は、出雲王朝の推移が、その後の史書でどう描かれているかを調べることにした。
4世紀初頭から、中国は北と南に分裂し、南北朝時代を経て589年隋に統一される。
しかし、618年、隋は唐に滅ぼされてしまう。
隋書は、その唐代になってから、魏徴等の編纂で636年に編纂は完了し、最終的には656年に完成した。
そして、さらに南北朝時代から隋に至る史書として、『北史』と『南史』が、李延壽により659年に完成している。
同じ唐代でもあり、隋書の完成からそれほど経過していないため、あまり変わったことは出て来ないと思われた。
だが、逆に、出雲王朝のその後の推移を調べるには、ホットな情報が得られる可能性もあると恒之は期待した。
北史と南史をそれぞれ見たが、北史は隋書を、南史は宋書を基本にしていた。
恒之は、その2つの史書に目を通していたが、その内容に大きな疑問を抱いた。
そこで恒之は、隋書と北史を並べ、双方を比べてみた。
そうすると、過去の史書の内容が2か所に挿入され、そして、ある部分は削除されているのが分かった。
最初は、単に過去の資料を補充し、特に不要と思われる所を割愛したのかとも考えた。
ところが、よくよく見直してみると、全く歴史が変わってしまっている。
南史にも同じように手が加えられていた。
『どうも変だ。この修正は、認識の相違から来るものなのか、あるいは勘違いなのか。もしそうでないとしたら、これは故意による歴史の操作、つまりは、意図的な改竄だ』
恒之は、改めて過去の史書を読み直した。
漢書、三国志魏書、後漢書、宋書、南斉書と唐代以前に記された史書と、唐代の隋書には、特に操作があったようには感じられなかった。
ところが、唐代の梁書、晋書、北史、南史における倭国を記した部分には、ある共通した意志が感じとられた。
『これは、偶然ではなく、明らかに唐代の倭国に対する考え方から来る、意図的な歴史の改竄と言わざるを得ない』
だが、もう少し検討しようと、恒之は史書をそれぞれ見直すことにした。
それからしばらくは、仕事が忙しく珠に目を通すくらいだった。
「ねえ、連休中はみんな揃うけど何処かへ行く?」
夕食後、恒之がコーヒーを入れていると、洵子が聞いてきた。
「毎年のことだが、この連休中は忙しくてのんびりしてられないんだよなあ」
「そうよねえ」
「まあ、食事に出かけるくらいかな」
「それでも、私的にはうれしいんだけどね」
「2人が帰ってきたら相談しようか」
「そうね」
そんな話をしているところに、由美からメールがきた。
【3日に帰ります。それと、玲子から耳寄りな話を聞きました。藤原氏に関わることなんだけど、ちょっと驚きです。帰ったらお話します】
「由美は、3日に帰ってくるそうだ。明代はどうするのかなあ」
「そう、連休が待ち遠しいわね。明代は、休みになればどうせ帰ってくるわよ。食事や洗濯のことを考えたら寮にいるわけ無いわ」
「きっと、そうだろうな」
恒之は、話をしながらも、由美の言う藤原氏のことを考えていた。
『耳寄りな話って何だろう』
恒之は、洵子と少し違った意味で待ち遠しく思った。
それからも、恒之の頭の中は、中国の史書のことばかりだった。
他のことが上の空というほどでは無いが、仕事や身近に起きるいらいらするようなつまらない事も、古代史を考えることで払拭できた。
『わが国の歴史は、ある意味、唐に作られたとも言えるかもしれない』
恒之は、調べていけばいくほど、唐の陰が大きくなっていくのを感じた。
そして、3日になり由美が帰ってきた。
しばらく振りに、西山家に賑やかな時が戻った。
「由美ちゃん、その服よく似合ってるわね」
「お母さんありがとう。でも、結構安かったのよ」
夕食も、今まで以上に盛り上がっていた。
「お姉ちゃん、彼氏が出来たんじゃない」
「いきなり何言うのよ」
「だって服の趣味が変わったし、それに、そのネックレスもお姉ちゃんが買ったとは思えないな」
「そんなことないわよ」
「あら、別に良いじゃない。20歳も過ぎればそんな人がいても不思議じゃないわ」
「ちょっと、お母さんまで」
「お母さんも、お父さんとお付き合いするようになったのは20歳の頃だったわよ。ねえ、お父さん」
「そ、そうだったかなあ」
洵子も一緒に会話に加わっていたが、恒之としては、そう簡単に同意できる話でもなかった。
由美には、何よりもまず、やるべき事を成し遂げて、それから生涯の伴侶を探して欲しかった。
男女関係に左右され、本来進むべき道に進めなかった例を身近に見てきた恒之の、率直な思いであった。
しかし、親が口を挟んで余り良い結果にならないというのも恒之の実体験であった。
恒之は、早々に食事を切り上げると、居間でパソコンの電源を入れた。
『最近メールが来なくなったのは、彼氏が出来たからだったのかな』
娘に彼氏が出来るという事に、まだ慣れていない自分がいることに気づく恒之だった。
どう受け止めたら良いのか、不安と寂しさを感じたが、画面に史書が出てくると次第にそちらに没頭していった。
「お父さん、相変わらず古代史ね」
「ああ、由美か」
由美が側に来ているのにも気づかなかった。
「正月に帰って来た時に、隋書まで見ただろう。その後の史書を読んだら、大変なことが分かったよ」
「大変なことって?」
「ほら、これを見てごらん」
恒之は、幾つかの史書のコピーをテーブルの上に広げた。
「これが北史だよ。南史とともに隋書の次に完成した史書だ」
由美は、その北史を手にとって内容を見た。
「あら、女王国へ行く道順が書き込まれているけど、行き先が邪馬臺(台)国になっているわ。三国志では、邪馬壹(一)国となっていたわよ」
「つまり、邪馬壹(一)国が、邪馬臺(台)国にされてしまったということだよ」
「ええっ、どういうことなの」
由美は、さらにもう少し先も見た。
「卑弥呼が亡くなって、次の女王になったのが、臺(台)與とされているわ。これも、壹(一)與だったはずよね」
「変だろう。最初は、書き写し間違いではないかとか、勘違いではないかとか思ったんだが、どうもそうではないんだ。この北史は、隋書の改定版みたいなもので、ほぼそのまま書き写されているが、一部書き込むことで内容は全然違ったものになっているよ」
「何だか変よね」
恒之は、隋書と北史のコピーを並べた。
「ほら、この部分に6行ほど書き込まれているだろう。それが無い隋書では、倭(人偏に妥)国には、邪馬臺(台)があり、そして女王卑弥呼のいる倭奴国もあったとなり、別々の国として説明がされていた。しかし、北史では、本来邪馬壹(一)国へ行く道順と、そこには邪馬臺(台)国があったという文章が入ることで、女王国と邪馬臺(台)国の両者は同一の国となってしまった」
「手品みたいね」
「それが、勘違いでないのは、わざわざ、邪馬臺(台)国とは即ち倭(人偏に妥)王の居る都であると注釈までつけている。壹(一)ではなく、中央官庁としての臺(台)であるとその意味まで記しているんだよ」
「どうしてそんなことをしたのかしら」
「さらに、倭国は呉の太伯の末裔だと自ら述べているとまで書いている。こんなこと唐代より前の史書には無かったよ」
「大陸から多くの人はやって来てはいるんだろうけどね」
「つまり、倭国は中国の系統であると言っているんだよ」
「中国の?」
「この北史の操作には、ある考え方の下に隋書の手直しがされている」
「どんな?」
「出雲王朝隠しだよ。つまり北方騎馬民族によるこの列島支配を歴史から消そうとしているんだよ」
「本当に?」
「呉の太伯の末裔であるということは、北方騎馬民族の影響を消したいということだ。この列島は、歴代中国のテリトリーだったというかなり強い意志がそこにはある」
「そうなの」
「2つ目の挿入部分では、三国志にある卑弥呼の死と壹(一)與が次の女王となる文章が入っているよな。それが、臺(台)與とされているのも臺(台)は出雲でなく女王国だとしたいからだよ」
「なるほどね」
「そして、その直ぐ後に『至開皇20年、倭(人偏に妥)王姓阿毎』と続くだろう。ということは、隋書に出てきた邪馬臺(台)にいる倭(人偏に妥)王は、その女王国から続く倭(人偏に妥)王だと読み取ることになってしまう」
「出雲王朝が、邪馬壹(一)国に移動、あるいは吸収されてしまったことになるわね」
「そうなんだよ。まるで、古事記の世界だよ。すると、その女王は天照大御神として奉られていったということなんだろうか」
「出雲王朝隠しの源流は、唐にあったのかしら」
「隋書では、最後、隋の使者が来て倭(人偏に妥)王と接見する場面があっただろう」
「そうね」
「ところが、その場面がすべて削除されているんだよ」
「削除?」
「そう。そして切り落とされて、その前後が繋ぎ合わされている」
「切り貼りね。そんな所を何故カットしたのかしら」
「それによって、まったく別の意味になってしまった」
「別の意味に?」
「そう。ほら、ここからここまでが削除されているだろう」
「そうね。でも、上手く繋がったものね」
「みごとだよ。その部分の、もともとの意味は、使者の清が王と会見して、最後、使者や貢物も合わせて清をお送りしたとあった。ところが、その接見部分がカットされたので、文章の意味は、使者の清が、倭(人偏に妥)王のいる都に着き、その倭(人偏に妥)王は、清と一緒に貢物を持って隋にやって来たとなるんだよ」
「ええっ、それはどう考えても変ね」
「文字のマジックだよ」
「そんなの歴史の改竄でしかないわ」
「こんなことは、北史だけだろうかと唐代に書かれた他の史書も見たんだよ」
「どうだったの」
恒之は、別の資料を出した。
「これは、北史と同じ人物が作成した南史だよ。これは、宋書を書き写しているんだが、前後に別の文章をつけている」
由美もそれを見たが、宋書では倭の五王に関わる内容だけだったのに、かなり長い文章が前後に加えられていた。
「三国志にある邪馬壹(一)国の風俗に関する紹介文が加えられているんだよ。そうなると、倭の五王は、女王国の末裔だということになってしまう。宋書の部分の次には、邪馬壹(一)国の南に続く国を紹介する文章が加えられている。倭の五王のいた国の南には、邪馬壹(一)国の南にあったとされる国が書かれている」
「そうなると、倭の五王は、場所も系統も卑弥呼がいた女王国にあったことになってしまうじゃない」
「すっかり取り込まれている。636年に完成した梁書は北史と南史を合わせたような内容だよ。倭は、呉の太伯の末裔だと自ら言っているとあり、邪馬壹(一)国へ行く道順が書かれ、行き先は邪馬臺(台)国とされている。そして、卑弥呼の次に臺(台)與が女王になり、倭の五王が後に続く。まったく同じ手法だよ」
「隋の使者が邪馬臺(台)国である倭(人偏に妥)国、つまり出雲王朝である大国に行ったのは、唐の時代からすればほんの数十年前よ。そして、隋書が書かれたのは同じ頃だから、邪馬臺(台)は、卑弥呼のいた邪馬壹(一)国ではないと分かっていたはずよ。隋書には、その道順まで記されていたわ」
「竹斯国の東に秦王国があったと書かれていたが、それも一切触れてない。倭国は中国の末裔と描き、卑弥呼のいた邪馬壹(一)国をこの列島の臺(台)に仕立て上げた。出雲王朝が、中国の史書に登場するのは、後漢書では邪馬臺(台)があるという程度だったから、主には宋書と隋書なんだよ。出雲王朝の歴史はわが国には残されていないから、本当にこの二つの史書は貴重なんだ。ところが、唐は、この二書を根底から作り変えてしまった」
「どうして、そんなことをしたのかしら」
「この列島に対する覇権は、中国にあると考えていたとしか思えないよ。それがこともあろうに、この列島が北方騎馬民族に制覇されてしまっていたんだから、唐にしてみれば許せなかったんだろう」
「でも、宋書と隋書が残っていて良かったわね」
「そうだよ。危うく出雲王朝の姿が完全に消されるところだったよ」
「宋書と隋書があったから出雲王朝に行きつけたようなものだものね。隋書には、大国の王の言葉まで書かれているんだから、本当に貴重よね」
「唐は、相当出雲王朝に対抗意識があったようだ。北方騎馬民族で夷人だなどと自ら言う国王の言葉など削除の対象でしかなかったのだろう」
「そうね、でもそんな対抗意識だけで重要な会見の部分を削除したのかしら」
「えっ、どういうこと?」
「よく分からないけどそんな気がしただけ」
「どうなんだろう。何か都合の悪いことでも書かれていたんだろうか」
恒之は、隋書に出てくる王の言葉に目をやった。
中国の史書に唯一登場するこの列島の大王の言葉である。
その最後は、『冀聞大國惟新之化』で結ばれている。
「『大國惟新之化』ということは、大国を維新、かなり大きく改革しようと考えていたんだろうなあ。つまりは、大化ということか。…大化?」
その時、明代が居間に入ってきた。
「ねえ、お姉ちゃん、お母さんが明日の夕食はどこかへ行こうかなあって言っているけど。どこがいい?」
「明日の夕食ねえ」
由美は、明代の言葉で立ち上がり、洵子のいる台所へ移った。
恒之は、しばらく隋書を見ていたが、次第に睡魔が襲ってきた。
そして、古代史探索の続きは、次の日に持ち越しとなった。
|




邪馬台国発見
Copyright (C) 2008 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.