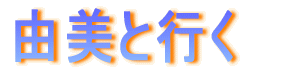|
28、
3月も下旬になるというのに、その日は、朝からみぞれ混じりの雨が降っていた。
恒之は、パソコンの画面に出した天気図や降雨状況を見ていた。
「よし、今日行こう。午前中で雨はあがるよ」
「今日の天気は、あまり良くないみたいよ」
「大丈夫、午後は晴れるよ」
「そう、じゃあ、明代を起こしてくるわね」
4月に入ると、仕事の関係や明代の入学式を控えてとても行けそうになかったので、恒之は少々天候が悪くても、今日行くしかなかった。
家を出る頃は激しく雨が降っていたが、米子に近づくにつれて小雨に変わった。
「ようやく雨が小降りになったよ」
「このまま止んでくれるといいのにね」
洵子も少し心配そうに車窓から空を眺めていた。
「心配しなくても、雨は午前中であがるよ」
「本当かなあ。朝はかなり冷え込んでいたよ」
明代も不安そうにしている。
「『お父さん気象台』を信じなさい」
「あてにしていいのかなあ」
天候の具合を心配しながら、車は米子から北に向かい、境港に近づいた。
「あっ、雨が止んだわ」
「本当だ。お父さんの言ったとおりね」
「だろう」
そして、島根半島に掛かる境水道大橋を渡り始めた。
「ほら、お母さん、見て。雲が山を登っていく」
「わあ、何これ。あちこちから、雲が沸き立つように登っていくわ。こんなの初めて見るわ」
恒之が、高い壁のように連なる前方の島根半島を見ると、幾筋もの雲が斜面に沿って上がっていた。
雨上がりの時に見られる現象のように思えた。
「こういうのを、八雲立つと言うのだろうか」
「神々しいわね。やっぱり出雲よね」
「神、雲、熊。これらは、みな共通しているそうだよ」
そう言っているうちに大橋を渡り終えた。
「まるで、神域に入ったみたいに思えるわね」
「ここは、以前の出雲国嶋根郡になるよ。まずは、美保関灯台に行ってみよう」
半島の南岸沿いの道を東に向かった。
「中国の史書に出てくる『山嶋に依りて』といったような道だよなあ」
「あっ、男女岩(めおといわ)だって」
「本当だ。伊勢にあった夫婦岩とそっくりだよ」
恒之は、近くに車を止めて撮影した。
洵子も、車から降りてきた。
「ちょっと南東に向いているようだから、伊勢とは逆に、冬至の頃に2つの岩の間から朝日が昇るのを見れるかもしれないよ」
「冬に来ることはできそうね」
「可能かもしれないけど、寒い時期にここまで来るのは、それはそれで大変かな」
「そうね。それに、その時期は特に天候が良くないから、綺麗な朝日が見れるかどうかは分からないわね」
2人は車に戻り、また東へ向けて走った。
そして、島根半島の東端にある美保関灯台に着いた。
そこからは日本海を一望することができた。
灯台周辺は、強い風が吹いており、その下に見える北岸の絶壁は、少々怖いものがあった。
「あっ、お母さん、ほら、船が見える」
「きっと、隠岐島とを結ぶフェリーね」
「乗ってみたいわ」
「いつか、お父さんが隠岐島に行こうと言っていたけど。旅行雑誌を見ただけで終わってしまったわね」
「ええっ、どうして行かなかったの?」
「どうも、旅行雑誌を見ているだけで行った気分になってしまったみたい。お母さんは、見れば見るほど行きたくなるんだけどね」
「でも、お父さんは、時々出かけているでしょう。隠岐島にも行こうよ」
「お父さんはね、古代史に関わるところだと行く気になるそうよ。いろいろ調べられて写真が撮れたらそれでいいみたい」
「なるほどね」
恒之は、2人の会話を聞きながら周囲の撮影を済ませた。
「北岸は、すごい絶壁ばかりで、とても人が近づけるような場所ではないよ。さあ、次の場所へ行こうか」
「ほらね」
洵子と明代が顔を見合わせていた。
「次は美保関神社だ」
「全国にたくさんある恵比寿神社の総本社ね」
先ほど来た道を車で戻るとすぐに着いた。
そのあたりは、漁港になっていた。
「恵比寿さんは、釣り竿と大きな鯛を抱えているよなあ。その神社が漁港の側にあるというのもそれらしいよ」
「そうね。事代主命は、この港から船に乗って漁に出ていたのかもしれないわね」
「先ほどの灯台から、事代主命が釣りを楽しんだと言われている沖の御前島が見えていたよ」
「釣りを楽しむ神様って、他には聞かないよね。何か親しみを持たれていたように思えるわ」
「そうかもしれない」
無料駐車場という表示があったので、恒之は漁港の側にある空地に車を止めた。
少し歩いて美保神社へ行くと、その参道には、他にも参拝者の姿があった。
山ばかりの島根半島東部にあっては、場所が限られているが、それでもかなり大きな本殿が建てられていた。
境内に入ると、20歳過ぎと思える女性が、拝殿の前でじっと手を合わせていた。
その一心に拝んでいる姿が、恒之には印象的だった。
恒之は、本殿をいろいろな角度から撮影した。
「ここの神紋は、亀甲に三だよ。きっと、祭神の三穂津姫命からきているのだろう」
「他にもあったみたいよ」
「よく気がついたなあ。亀甲に三つ巴と亀甲に渦雲があったよ。どちらも雲を意味しているようだから、雲が重要なポイントのようだ」
そんな話をしながら恒之がふと見ると、先ほどの女性は、まだ手を合わせていた。
誰かのことを偲んでいるのだろうか。
「ずっと手を合わせているわね」
洵子も気づいていたようだが、しばらくして、その女性は参拝を終えて帰っていった。
少し気になったものの、恒之には彼女の思いを知るすべはなかった。
「ここは、本殿が2つ並んでいるのね」
「そうだなあ。めずらしいよな」
拝殿の後ろには、エックス状に交差した千木と屋根が二棟見えている。
「三穂津姫命も事代主命も同等に奉る必要があったのかな」
そして、美保神社を後にすると、次は半島を西に向かった。
30分ほど走り松江市に入ると、昼が近くなっていたので、軽く昼食を済ませた。
そこの駐車場からは、すぐ側に宍道湖が見えていた。
「千鳥公園だ」
「そう云えば、この前話していたわね」
「ここもちょっと見ておきたかったんだ。あっ、そうだ」
恒之は、用意してきていた資料を手にして、宍道湖の湖畔へと向かった。
少し肌寒かったが、5百メートルほどある公園内の道を、数名の男性がジョギングしている姿が見えた。
「あれが嫁が島ね。あの島の背後に沈む夕日は、とても綺麗だったわね」
数年前、家族で宍道湖の夕日を見に来た。
穏やかな湖面に映る秋の夕日は、あまりにも綺麗ではあるが、どことなく寂しさも漂っていた。
「千鳥公園の由来が、何処かに表示してないだろうか」
「千鳥公園の?」
「千鳥公園とどうして名づけられたのか知りたいんだよ」
「どうかしら」
その周辺を探したが、そういう表示は見当たらなかった。
「ほら、電柱に千鳥とあるわ。このあたりの地名は千鳥みたいよ」
「そのようだ。んんっ、これは何て書いてあるのだろう」
芝生の中に、石碑があった。
「漢字ばかりね」
「漢詩かなあ」
「何て書いてあるのか意味がよく分からないわね」
「この宍道湖について、何か思いを記しているのだろうか」
「そんなの見ていても分かる訳ないわよ」
明代は、少々退屈ぎみのようだ。
「そうだな」
そう言って、恒之はその場を離れようとした。
「ちょっと、これは…」
最後の方の文字に目がいった。
「どうしたの?」
そこを立ち去ろうとしていた洵子もまた戻ってきた。
「ほら、最後のあたりが『誰ぞ知るや肇国』と読めるだろう」
「そうね。それって、何か意味深ね」
「肇国とは、国の始まり、建国のことだよ。ということは、出雲国あるいは日本、または古く倭国のことだろうか、その国の成り立ちの事情を誰が知っているのだろうと言っているようだ」
「この人はそれを知っていたということかしら」
「そこまでは読み取れない。中国の史書より難しいよ。何とか、もう少し詳しく知りたいなあ」
「微妙なところよね」
恒之は、その並んでいる漢字の意味を読み取ろうとしたが、とても分かりそうになかった。
仕方がないので、そこを離れ、湖畔の道を歩いた。
「ねえ、鳥がたくさんいるわよ。千鳥かしら」
「さあ、どうだろう」
恒之が湖面を見ると、たくさんの鳥が群れをなして浮かんでいた。
「でも、宍道湖ってどこかしら寂しさを感じるのは何故だろう。そう思って見るからだろうか」
「何が?」
恒之は、西は出雲市方面に続く湖面を眺めながら、近くにあるベンチに腰掛けた。
洵子と明代も横に座った。
「柿本人麻呂の歌でどうもよく分からない歌があってね。その歌が、実はこの宍道湖を詠っていたのではないかと、最近思うようになったんだよ」
「あの人麻呂が、この宍道湖を詠っていたの?」
「さあ、まだ何とも言えないが、条件はそろってきているんだ」
「ふうん」
「そのこともあって、この千鳥公園に寄ったんだよ」
「そう。それで、人麻呂は、どんな歌を詠んでいたの」
「これなんだ」
「あら、わざわざ資料も持参してきていたのね」
「今回の重要なポイントだからね」
恒之は、万葉集をコピーした資料を洵子に渡した。
「ほら、この歌だよ」
洵子は、恒之が指し示す歌を見た。
そこには、原文や現代文訳も書かれていた。
淡海乃海 夕浪千鳥 汝鳴者 情毛思努尓 古所念
近江の海 夕波千鳥 汝が鳴けば 心もしのに いにしへ思ほゆ
近江の海の 夕波千鳥よ お前が鳴くと 胸が締め付けられるほどに 昔のことが偲ばれる
「近江の海となっているわね。ということは、琵琶湖ではないの?」
「そのように解釈はされているよ。でも、琵琶湖は確かに大きいが海ではないよ。それに、人麻呂が偲ぶほどの古いことが思い当たらない。出雲には少なくとも3世紀頃からスサノオや大国主命を中心とした勢力がいて、中国の史書に邪馬臺(台)と表現される大倭王のいる大国があったとも思われる。そして、それが、藤原の勢力に征服されてしまった」
「滅んだ出雲王朝ということね」
「人麻呂が偲んでいたのは、その出雲王朝ではないかと思えるんだよ。万葉集には、大王という表現もたくさん出てくるよ」
「夕波とあるから、夕方、宍道湖のほとりで佇んでいたのかしら」
「宍道湖は、海と繋がっていて真水ではないから、純粋には湖とは言えない。でも、海ほど塩分は濃くない。だから、淡い海なんだよ」
「宍道湖は、河口で獲れるシジミ貝の産地でもあるよね」
「淡水にいる鯉や海にいるスズキが同居しているんだ」
「宍道湖七珍は、有名よね」
「淡い海、滅んだ出雲王朝、夕暮れ時の宍道湖の風景、そして、千鳥。その歌の条件が揃っているだろう」
「そうね。でも、本当に淡海は、滋賀県の近江ではなく宍道湖なのかしら」
「他の歌には『鯨魚(いさな)取り
淡海の海を』という表現もあるんだよ。鯨や魚を取りに沖へ出て行くと詠われている。でも、琵琶湖に鯨はいないよ。宍道湖は、海に繋がる港、つまり津、大きな津なんだ」
「なるほどね」
「そして、人麻呂は、このあたりで綺麗な夕日を眺めながら、千鳥の鳴く声に滅んだ出雲王朝を偲んでいたのかもしれないよ」
「出雲も万葉集の舞台だったのかな」
「その可能性は高いと思うよ。じゃあ、次は出雲大社の方へ行こうか」
「そうしましょう」
3人は、左手に宍道湖を見ながら出雲市へと向かった。
|